RockzGoodsRoom > Outing > Outing2025 >
RockzGoodsRoom > Goods >
 |
||
| 第2庁舎は村野藤吾設計ではない |
| 集合は北西角の武庫川沿いのほうです。 |
 |
 |
|
| 本庁舎 | L字型の配置 |
| 駐車場側から入ると、現在は1階なんですが、武庫川や西側道路から入ると、高低差があって現在は2階になっています。 本庁舎は竣工以来、英国式にG階、1階・・・4階としていたのを、2023年(令和5年)に第2庁舎が建設され、業務開始にあわせて、1階〜5階と変更しました。 日本人には英国式の階数表示はなじめませんでしたが、43年間その表記でしたね。 集合は北西角の武庫川沿いのほうです。 |
 |
 |
|
| ここは2階 | 向こうの端が集合場所 |
| 受付のテーブルが出ていました。 受付しますよ。 |
 |
||
| 資料と参加者証 |
| 当日配布の資料が、PR等も兼ねているものが多いですが結構ありました。 しばらく外で待っていましたが、もう入っていいですよとのことで入ります。 4階の南端の会議室に向かいます。 |
 |
||
| この一番奥へ |
| あら?1番に入室出来ちゃったので、一番前の席に座りましょう。 まずは、京都工芸繊維大学 笠原一人准教授によるレクチャーです。 京都工芸繊維大学には、村野藤吾の図面が多くあります。 何故なのか以前から疑問で、今日時間があれば笠原先生にお聞きしようと思っていたのですが、時間がなかったので帰宅後調べてみると、京都工芸繊維大学美術工芸資料館の資料によると、概ね以下の通りのようです。 1991年(平成3年)、京都工芸繊維大学名誉教授で、初代美術工芸資料館館長であった中村昌生氏が村野藤吾の建築作品を案内してもらっている際に、村野事務所の岡林氏から「美術工芸資料館で建築図面を預かってもらえないか」という打診を受けたとのこと。 翌年の1992年(平成4年)に村野藤吾の没後、事務所を引き継いだ子息の村野漾氏からも「村野の図面は全部京都工芸繊維大学の美術工芸資料館んへ寄贈することに決心しましたから宜しく」との手紙があったそうです。 当時、資料館専任の助教授であった竹内次男氏の父が村野事務所の戦前の所員だったこともあったようです。 そして、1994年(平成6年)から図面が持ち込まれたということらしいです。 笠原先生の自己紹介とともに、村野藤吾の紹介も改めて。 昨夜の、新美の巨人の話も出て、内田有紀さんに建築のことを紹介していたのは笠原先生でしたね。 日本の建築家は、現代では、安藤忠雄や隈研吾、SANAA(妹島和代、西島立衛)坂茂など、建築界のノーベル賞 と呼ばれるプリツカー賞受賞者が世界的に有名となりますよね。 過去の受賞者には、丹下健三、磯崎新なんて名前も。 しかし、そこには村野藤吾の名は挙がりません。 近年、海外でも村野藤吾への関心が高まっているとのことで、今年の2月には、初めてフランス・パリの日本文化会館で200名以上の人が集まるシンポジュウムが開催されたそうです。 村野藤吾の設計は、モダニズム建築、機能性・合理性を重視する建築とは違い、 過去の芸術様式からの分離と新しい造形芸術の創造を目的としたセセッション建築を取り入れていて、そんな自由な様式が多く、村野自身に憧れがあったとのことでした。 早稲田大学で学び、大林組に就職が決まっていたそうですが、渡辺節建築事務所に入ります。 丹下健三とのライバル関係というのがよく言われますが、1948年(昭和23年)の広島平和記念カトリック聖堂のコンペにあると言われます。 ちなみに、国の重要文化財の設計でと言えば、村野藤吾は4と一番多く、丹下健三は2ということだそうです。 村野藤吾の紹介の流れで、のちほど伺う宝塚カトリック教会の簡単な説明も受けます。 宝塚カトリック教会の設計には、建築家であった、日建設計の創業者の一人、長谷部鋭吉との関係があったと言います。 村野藤吾は、長谷部鋭吉を師と仰ぐほど敬愛しており、その影響で長谷部鋭吉が住む、宝塚市清荒神に移り住みます。 長谷部鋭吉は、晩年近くに自身が設計した芦屋カトリック教会で洗礼を受け、清荒神の自宅兼アトリエに祭壇を設けて祈りの場として提供していました。 宝塚カトリック教会は、元々は長谷部鋭吉が設計するはずでしたが、1960年(昭和35年)にお亡くなりになり、信者の願いを受け、それを引き継いだのが村野藤吾ということでした。 その村野藤吾も、晩年自らが設計した西宮トラピスチヌ修道院(シトー会西宮の聖母修道院)で洗礼を受けました。 形はハイヒールを逆さまにしたような形。また、村野藤吾氏の当時に手記によると、「大洋を漂いつづけていた白鯨がようやく安住の地をみつけ岸辺に打ち寄せられたとでも申しましょうか」とのことで白鯨を模しているとも言われています。 外壁と地面との境目があいまいで、地面から生えるような形状は、村野藤吾晩年の特徴でもあるそうです。 モダニズム建築では絶対やらない手法で、そもそもモダニズムでは何かをイメージさせるようなものはNGとされていました。 それが現代の価値観多様の時代になり、村野藤吾の建築が再評価されてきたのではとのことです。 さて、宝塚市役所です。 村野藤吾には、市役所に必要な機能として、「市民ホール」があるということを固持していました。 建築とは表現物であり、時代や建築家としての人となりが現れます。 公共建築には公共建築ならではの表現がありますよねとのこと。 丹下健三も市民ホールを提唱しています。先代の東京都庁舎や香川県庁舎などは、誰でも使える開かれた空間としての市民ホールで、旧東京都庁舎では岡本太郎の、香川県庁舎では猪熊弦一郎の壁画がそれぞれあります。 民主主義を象徴する課のような市民ホール。ということです。 ちなみに、東京都の小池百合子知事は、神戸の甲南女子中学校・高等学校に通っていました。 この甲南女子中学校・高等学校は村野藤吾の設計によるもので、ちょうど小池知事が高校に進学した時に村野藤吾設計の公社が完成しているということだそうで、村野藤吾の校舎で学び、丹下健三の庁舎で働いているということになっています。 村野藤吾は、横浜市庁舎や尼崎市庁舎も手がけましたがベランダで閉じられた内部の空間としての市民ホールを備えています。 閉じた空間で何もない。市民が集まるホールです。 ヨーロッパの市民ホールがこのような形式で、儀式や市長の就任式などで使われるそうです。 村野藤吾が好きであった、2つの建築があるそうです。 ひとつは、ローマのパンテオン、そしてもう一つがストックホルム市庁舎です。 このストックホルム市庁舎は1909〜1923年にかけて建設された、建築家・ラグナル・エストベリの設計によるものですが、今でもノーベル賞の晩餐会が、市民ホールである「青の間」で行われます。 というあたりで、座学としてのレクチャーを受けました。 質問コーナーになったので聞いてみます。 宝塚市庁舎は、村野藤吾の晩年の作品と思うが、ストックホルム市庁舎の流れを取り入れてはいると思うが他の村野藤吾の庁舎建築とは雰囲気が違う。 晩年ということで志向の変化などはあったのだろうか・・・。ということ。 笠原先生曰く、ヨーロッパのスタイルを固持していたのは間違いなく、その上で、宝塚というイメージと、武庫川沿いということでの影響はあったと思われる。ただ、晩年となった1970年代の作品には、古典回帰になっているようなものも多く、同時期の関大一高などは同じようなデザイン性を持っている。とのことでした。 名が知れた建築家が、自分の建築の話をよくするそうです。 丹下健三は自分の建築を大いに語ったそうですし、安藤忠雄もプロボクサーから建築家に転身してというようなエピソードもインパクトありますよね。 しかし、村野藤吾は自身でほとんど語ってこなかったそうです。 帰宅後、いろいろと調べていると、面白いブログ記事みつけました。 村野藤吾設計の八ヶ岳美術館にて、建築家・藤森照信先生による講演会「村野藤吾と八ヶ岳美術館」の内容です。(こちら) 本当に語らない人だったようで、今となって研究されるのもわかる気がしますね。 他にも2013年(平成25年)に発生した、宝塚市役所での放火事件の際にはベランダが役に立ったと思うが、そこも見越して設計されていたのかという質問をされた方も。 そこまでは見越していなかったでしょうけど、モダニズム一辺倒ではベランダはなかったでしょうねぇ。 最後にひとつお話が。 日本現代建築に多大な功績を残した建築家・村野藤吾を記念し、建築界に感銘を与えた建築作品を設計した建築家を 毎年ひとり選んで与える賞、「村野藤吾賞」があるそうです。 この授賞式は東京と、ここ宝塚市役所で年替わりで行うそうですが、今は市民ホールは執務室になっているので授賞式には使えないですね。 村野藤吾賞、帰宅後調べてみると、受賞者はかなりすごい方ばかりでした。 では、少し休憩の後、庁内ツアーに出ます。 今日は特別に宝塚市役所の模型も出してきていただいていますので、拝見しました。 |
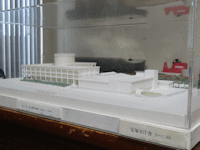 |
 |
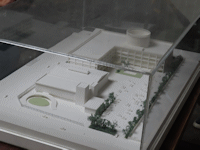 |
| 1/300模型 | 旧上下水道局庁舎のあった頃 | 村野事務所で作成したのかな |
| あと、事務局の方から紹介のあった、宝塚市庁舎のペーパークラフトも販売していたので、買ってみました。 解説冊子は笠原先生の寄稿があるようですね。 |
 |
||
| これです |
| 以前からこの存在は知っていましたが、窓口販売以外は定額小為替じゃないとだめとかなので、躊躇していたのですが今回は市の方が販売してくださるので、いい機会なので購入しました。 1部 600円ナリー。 ベランダに出ている方がおられあたので、出てみましょう。 この部屋からは、六甲山のほうが見えるのですが、今日は雲が低く山が見えないですね。 |
 |
 |
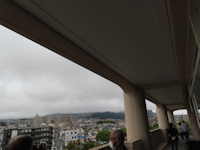 |
| 端部の収まりが細かい | 雲が低いなぁ | ベランダ天井も凝っている |
| 会議室に戻ります。 -13:40- では見学ツアーです。 まずは再度ベランダです。 |
 |
 |
|
| 通常の建築ではベランダ天井にここまで手をかけないなぁ | 収まりが単純でない |
| ルネサンス様式のような丸柱は、鉄骨柱にPC(プレキャスト・コンクリート)部材でカバーして丸柱にしているようで、その接合部がわかりますね。 また、村野藤吾の建築の特徴としてはできるだけ軽く見せるということを意識していて、このバルコニーでも柱と腰壁をあえて別として重たさを感じさせないようにしていると言います。 |
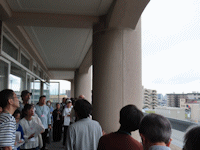 |
||
| 複雑な意匠 |
| 外壁にはレンガ積の部分もありますが、色目を均一にせず、色を変えることであえて味わいを出しているそうです。 積み方はフランス積み。イギリス積みにすると、目を細めると小口が連なる部分とで縞模様に見えてしまうからだそうです。 目地は通常の積み方に比べるとかなり厚いです。 こうなると、本来は重さがちゃんと下の方に伝わって行かないので、職人さんの仕事としては難しいそうですが、村野藤吾の好みなのだそうです。 |
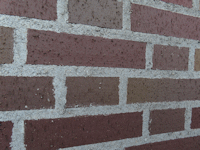 |
||
| 目地が太い |
| 窓は、壁からあまり奥まらないようにしているそうで、これは壁の厚さを感じさせないための工夫だそうです。 レンガなのに、壁が軽やかに感じます。 また、床と壁の取り合い部分は90度に接合せず、接合部分はアールになっています。 これは、ゴミが溜まらないようにする配慮だそうです。 |
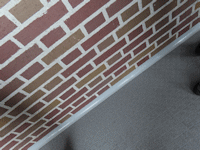 |
 |
|
| 直角に接合ではない | 職人さん大変 |
| ベランダや外壁の色はクリーム色っぽい色で、村野藤吾は真っ白は使わなかったそうです。このクリーム色っぽい色は好みだったとのこと。 |
 |
 |
 |
| 壁の位置で変化を | スリットを入れ一体化させない | 複雑だなぁ |
| 中に入って観て行きます。 村野藤吾のデザインの建築金物も多くあります。 |
 |
 |
|
| この家具は村野藤吾なのだろうか | こちらは村野藤吾のデザイン |
| 内部のパーティションは既製品かなと思っていたのですが、違うのかな。 押しても引いても操作性が秀逸なドアハンドルがあり、通称「牛の舌」と呼ばれるのがあるのですが、これは現在ではドアハンドレールメーカーのユニオンでT10という定番商品として販売されています。 |
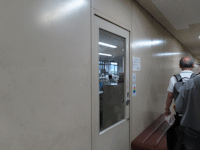 |
 |
|
| パーティション | ついているドアハンドルは村野藤吾デザイン |
| 特別会議室に入ります。 |
 |
||
| 特別会議室です |
| 壁は均一な仕上げになっており、モダニズムを感じさせますが、黒板を隠した扉が合ったり、天井廻りの部分は古典ヨーロッパ的な手法をとっているとのこと。 |
 |
 |
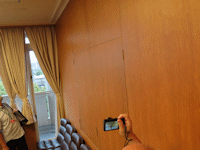 |
| 天井まわり | ベニヤの木目がきれい | 黒板を隠している扉 |
| 窓も、モダニズムでは1枚の大きな窓とするところを、細かく3分割していくところで、古典主義的にしています。 三層構成とするのは、古典ヨーロッパのお作法とのこと。 安藤忠雄は打ち放しコンクリートの建築物を建てましたが、それ以前はそのようなことをやろうと言う人がいなかった(作法に則ろうとしていた)だけなので、だからといって不作法というわけではないとのこと。 家具は村野藤吾のデザインなのかという質問がありましたが、特別会議室のは違うそうです。 村野デザインの家具もあるそうなのですが、すべては把握できていないようでした。 そういえば、尼崎市役所でも学芸員さんが調査してましたね。 |
 |
 |
 |
| 村野藤吾デザインのドアハンドル | 微妙に角度がついていて握りやすい | いいですねー |
| 議会受付の枠も、やはり分割されています。 |
 |
||
| 村野らしい |
| 議場に入らせてもらいます。 庁舎の上に載っている、円柱部分ですね。 現在、宝塚市議会がまだ開催中とのことで、机上に資料があるので議場内の撮影はNGです。 天井と壁の取り合い部分はあえて隙間をつくり、間接照明を入れて軽さを出しています。 その隙間部分は、議場の後のほうに行くと下がっているように見えます。 これは恐らくは音響効果のためでしょうとのこと。 外観は円柱形ですが、内観は多角形の感じがしますね。 議場の演台も村野藤吾のデザインのようです。 モノが転げ落ちないように台の端には落下防止に少し縁がついていますが、手前は台に置いた紙を引っ張って取ることを考えて縁がないです。 また、人の収まりがいいように真ん中は真っすぐではなく、窪む様な形になっています。 議場を出ます。 円柱の外は少し屋上緑化がありますね。 |
 |
||
| そして内側はレンガ調 |
| 見えないところまでこだわっていますねー。 議場に入らせてもらいます。 庁舎の上に載っている、円柱部分ですね。 現在、宝塚市議会がまだ開催中とのことで、机上に資料があるので議場内の撮影はNGです。 天井と壁の取り合い部分はあえて隙間をつくり、間接照明を入れて軽さを出しています。 その隙間部分は、議場の後のほうに行くと下がっているように見えます。 これは恐らくは音響効果のためでしょうとのこと。 外観は円柱形ですが、内観は多角形の感じがしますね。 議場の演台も村野藤吾のデザインのようです。 モノが転げ落ちないように台の端には落下防止に少し縁がついていますが、手前は台に置いた紙を引っ張って取ることを考えて縁がないです。 また、人の収まりがいいように真ん中は真っすぐではなく、窪む様な形になっています。 議場を出ます。 |
 |
 |
|
| 曲線の壁 | バックヤードはシンプル |
| 5階の議場傍聴席へ。 受付の家具は、椅子も含めて村野藤吾のデザインだそうです。 |
 |
 |
 |
| おー | 地面から空間をとる | 天板を張り出して連続性を見せないように |
| 受付台は上下に隙間を備えていて、やはり軽さを感じさせるようになっています。 議場の演台同様、三方は縁が少し上がり、手前側はくりぬかれたようになっています。 椅子は、事務で立ち座りがしやすいように、背もたれが低めになっています。 |
 |
||
| 背もたれが低い |
| 使い込まれたドアハンドルもいいですね。 |
 |
||
| 歴史を感じる |
| 4階から市民ホールを眺めるために移動します。 階段を下りて行きます。 |
 |
||
| 人研ぎの階段 |
| いわゆるビニハンドレールの手すりですが、これは1962年(昭和37年)に尼崎市役所で村野藤吾が初めて採用したものだそうです。 そして、これは以前お話を伺った、上野製作所によるものでした。 今では普通に市販品ですけどね。 |
 |
||
| ビニハンドレール |
| 市民ホールを上から眺めます。 現在パーテーションで区切って執務スペースとして使用しているので、こちらも机のほうは撮らないでくださいねってことです。 |
 |
 |
|
| 椅子が飾りに使われています | いねー |
| この廊下廻りのホール側の手すりや壁装飾に並ぶ椅子も上野製作所で北欧の椅子をカットして加工したものだそうです。 |
 |
||
| 市民ホールからのらせん階段 |
| 天井については、オリジナルではないそうですが、大和張りとしています。 小幅の板材を厚さの分だけずらして交互に張り合わせることで、凹凸と陰影を生み出す日本の伝統的な工法です。 |
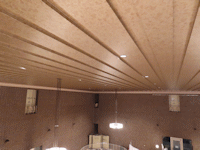 |
 |
|
| 大和張り | 天井照明 |
 |
 |
|
| 天井を照らす間接照明 | 中はLED球になっていた(笑) |
| 壁の装飾として飾られている椅子は、どう管理しているのかなぁ。 |
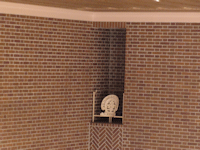 |
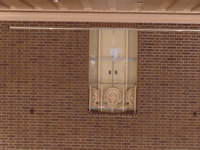 |
|
| ここは普段掃除できないね | ここは鎧戸開けたらできるかな |
| そして廊下廻りの執務室には、鎧戸が備わっています。 必要はないのですが、装飾として、また、市民ホールを利用している際に扉を閉じて音を遮る効果もあるとのこと。 |
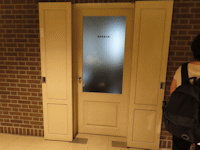 |
||
| 普段は開けっ放し |
| 廻り廊下の手すりの細工もなかなか考えられています。 |
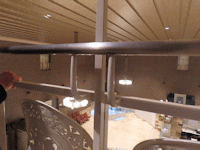 |
||
| スチールとステンレスの溶接かなぁ |
| 村野藤吾は和風建築の設計も手掛け、戦後の数寄屋建築の傑作として知られる佳水園(ウェスティン都ホテル京都内)なども設計しています。 笠原先生によると、数寄屋は「好き家」とも書け自由に造れる家とも言えますよねとのこと。 書院造が格式あるものに対して、自由な意匠を組み入れたのが数寄屋造となります。 洋風なものを取り入れるのでも、和風建築にこだわるとしても床柱を自然のものそのものを取り入れるように、自由な発想なのでしょう。 1階に降ります。 |
 |
||
| 期日前投票の際にはよく通る階段 |
| 市民ホールに直結するらせん階段、こちらも上野製作所の手によるものだそうです。 階段の踊り場は建築基準法により高さ3m以内ごとに踊り場が必要ですが、普通は中間に設けますが、村野藤吾はできるだけ下に配置しています。 これは、飛行機の着陸で直地直前に期待の角度を緩やかにするのと同じで、階段を下りてきた時にそのままの勢いで平面に至るのではなく、踊り場で勢いを和らげてスムースに平面を歩き出せるようにということに配慮した結果だそうです。 ヘタなパイロットは、勢いそのまま、着地のショックも大きいですからね。 |
 |
 |
 |
| ステキ | 浮かせるしつらえ | 6段目に踊り場 |
 |
 |
 |
| そこのパーティションどけてほしい・・・ | 最後の1段はやはり幅広い | 階段裏 |
| 階段と言えば、手すりの端部も引っかからないように曲げると言うのも階段を使う人への配慮ということです。 これは、当初の村野建築の時代には、女性はまだ着物を着る方が多く、袖が手すりに引っかかることのないようにという配慮からのようです。 村野藤吾が現場を訪れ、若い職人さんに聞いたことがあるそうです。 「階段では何が一番大事だと思うか」 職人さんたちは、踏面や蹴上などの段の幅や高さのこと、手摺の高さのことなどを言いますが、村野藤吾は「階段で一番大事なのは、階段の裏だ」と言われたそうです。 ということで、村野建築の階段の裏は手を抜かず美しいつくりとなっています。 |
 |
 |
 |
| 階段裏が美しい | 手摺 | 床は丸いモザイクタイル |
| 現在、普段はこのらせん階段は使用禁止となっています。 何故でしょうね。 しかし、今日は特別に歩いていいそうです。 |
 |
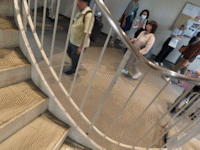 |
 |
| 踊り場 | 手摺 | ゆったりした蹴上・踏面 |
| 階段の最下段は床から浮くようなしつらえになっています。 そして上のフロアに直接接続ではなく、円形リングも含めた鉄骨構造のようですね。 2階に上がります。 |
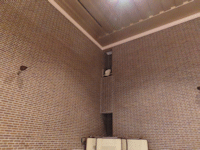 |
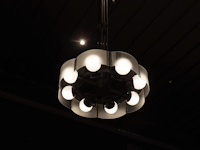 |
|
| 壁の連続性をあえて切っている | 下から見た照明 |
| 市民ホール内から再度見ます。 |
 |
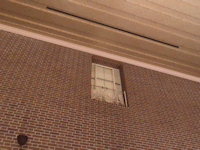 |
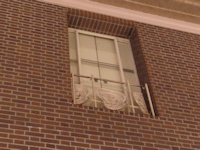 |
| 廻り廊下 | 飾り窓 | アップ |
| 壁はできるだけ連続性を持たせないよう、あえて不要な隙間をつくったりしています。 そしてこの部分も3分割。 ホール出入口となるような建具も3分割のルールで構成されていますね。 |
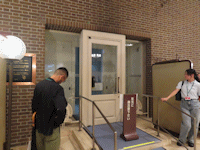 |
 |
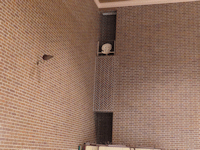 |
| なるほど | 廻り廊下の手摺も分割の美がある | 隙間の部分のレンガはあえて違う貼り方 |
| 廻り廊下を支える柱もオーダーに基づいた分割の美があります。 |
 |
||
| 柱 |
| ホール出入口のドアハンドルも使い勝手よさそう。 |
 |
 |
|
| シンプルだけどいい | ちょっとしたことなんだけどね |
| 円形内にあるらせん階段ですが、実は円の中に納まっているのではなく平面上では少しずれた配置にしていますが、これも流れるような感じを出すためでしょうか。 |
 |
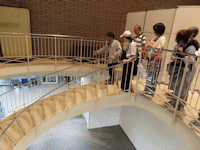 |
 |
| いいねー | ずれてる説明 | なるほど |
| 細部までのこだわりが、こうやって説明を聞くと面白いですね。 |
 |
||
| ここまで意識して見ていなかったなぁ |
| らせん階段を下ります。 |
 |
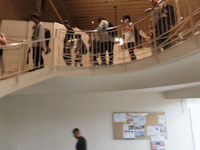 |
 |
| 今日は通れてよかった | 降りていきます | 階段裏がきれい |
 |
 |
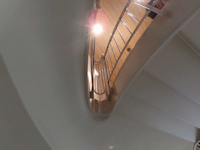 |
| 柱がほぼない | 制作大変だったろうなぁ | きれい |
| 1階から駐車場側の外部に出ます。 |
 |
||
| 駐車場側から |
| 車寄せのようにキノコのような物体があります。 言われてみるとそうですね。 車で来て、ここのエントランスからよく入るのですが、庇って感じでしか思っていませんでした。 |
 |
 |
|
| 言われてみればキノコ | 《misenさん撮影》 面白い |
| これには樋が見当たりません。 キノコの傘の中心部に雨水は流れるようになっていて、軸部分の中を通って雨水を処理しているそうです。 ベランダの柱の円柱がわかるように、梁の形状を工夫しています。 階高は1・2階より3階以上が低いです。 1階は西から見ると地階になるので、西から見ても基壇がどっしりと見えますね。 このあたりは、フランス・ルネサンス様式の影響とのことです。 |
 |
 |
|
| 3階以上は階高低め | ベランダの腰壁は出入り激しい |
 |
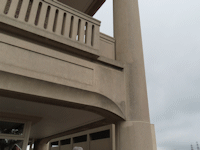 |
|
| 円形の部分は議場 | 納まりが複雑 |
| ちなみに、学生時代は建築史の様式とか覚えるの苦手だったなぁ。多分、興味がそう無かったのだと思います。 武庫川のほうに移動します。 市役所の食堂は「宝塚料理店」という名前です。 内部には青みのあるタイルが使われていて、このタイルはオリジナルのままだそうです。 今日は閉庁日で営業していませんが、「mono-koto-ba Takarazuka MOOK vol.5・華麗なる建築」ってこちらも笠原先生が寄稿されている、宝塚市商工課発行の冊子ですが、ここに内観が載っているのでとのことでした。 |
 |
 |
 |
| 宝塚料理店 | 内部 家具は後から |
キッチンのほうのタイルはわかりづらい |
| 屋外階段がありました。 |
 |
||
| ここも踊り場低い |
| 武庫川河川敷に降りて、外観を眺めます。 屋上の円柱部分は議事堂ですね。 宝塚市役所の外観は、グンナール・アスプルンド設計のストックホルム市立図書館だそうです。 |
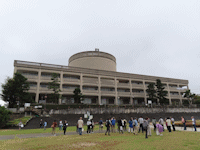 |
 |
|
| いいねー | 《Googleストリートビュー》 ストックホルム市立図書館 |
| この図書館は、「知識の壁」と呼ばれる壁一面の書架が中央円形閲覧室沿いにあり、360度書架に囲まれています。 この書架をモチーフにして、安藤忠雄も壁一面の書架を設置しているとのこと。 武庫川沿いの開けた景色にこの市役所があるのは荘厳ですね。 いつもは、武庫川を渡る宝塚大橋からしか見ませんが、河川敷から見ると一層いいですね。 茶室で如庵というのがあります。 織田信長の弟である織田長益(織田有楽斎)が建てた、国宝となっている茶室です。 京都・建仁寺で建造され、その後、東京・三井本邸に移築、神奈川に移築された後、現在は愛知・犬山にあります。 世の中には、「如庵の写し」とした茶室が多くあります。 優れた茶室の意匠を生かすため、忠実に、そっくりそのままにつくるのを 「写し」と言います。 でき上がった作品は「写し」であり、元になった茶室は「本歌」というそうです。 本歌は、和歌をつくるとき典拠にした歌を言います。 ただし、和歌では「写し」とは言わず、「本歌取り」と言います。 数寄屋は本家取りも多く、村野藤吾は自邸などに残月亭を写しました。 残月亭は、利休聚楽屋敷にあったという「色付九間書院」が「残月亭」として伝わっているものです。 元々、屋敷にあったものを息子の少庵が千家の再興に際し写し、火事や何度かの建て替えを経て、現在は京都の表千家にあります。 元神奈川大学教授であった西和夫氏(故人)によると、「写し」は真似とは言わないのはなぜかと言うことを新建築に寄稿されていました。
村野藤吾も数寄屋の精神で取り入れていく際には、このような先人へのリスペクトがあったのではないかというのが笠原先生の説明でした。 宝塚には、これから向かう宝塚カトリック教会と、宝塚ゴルフ倶楽部のクラブハウスが村野建築として残っています。 宝塚ゴルフ倶楽部は、フランク.L.ライトの落水荘を思わせるような建築だそうです。 内部はかなり改修されてしまっていて、オリジナルのふんいきはだいぶん薄れているようですが、こちらは、会員またはビジターでプレーする方しか入れないそうなので、ゴルフはしないので無理だなぁ。 レストランのみ利用もできないそうです。 また、市なりで見学ツアーがあればいいなぁ。 集合場所付近に戻ります。 市民ホールへの出入りの建具はかなりの重厚感がある、凹凸の激しい形状です。 このような形状は1960年代に流行ったそうで、竹中工務店がよく採用したデザインだったそうです。 |
 |
||
| 複雑だが規則性がある |
| 北東側の柱の足元には何かありますね。 車のぶつかり防止だそうです。 柱を守るような配慮が最初からされています。 御影石でつくってあり、しかも表面は叩き仕上げにしていて、こんなところまでこだわったつくりとなっています。 |
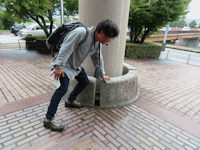 |
 |
 |
| 笠原先生の説明 | 車止めかぁ | 叩き仕上げ |
| またこの円柱の中心から、建物の門に向かって床レンガタイルの向きの交点をつないでいます。 このラインを出すの、職人さん大変だったろうなぁ。 半端モノを入れ込んで長さ調製したり。 |
 |
 |
 |
| 言われてみればラインが出てる | きれいに整えられています | よく見ると細かいもので調整 |
| 尼崎市役所で見たような壁の納まりもありますね。 |
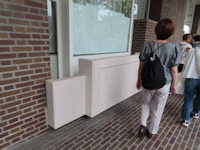 |
||
| 型枠大工さん大変だなぁ |
| -15:25- では、ここからはカトリック宝塚教会に移動します。 道路レベルに降りる階段も細部のこだわりを感じます。 |
 |
 |
 |
| 街灯は村野デザインとは違うかな | らせん階段上部の手摺と同じデザイン | 端部にもこだわり |
| 西側からは2階が1階のように見えます。 |
 |
||
| 2階は階高が高い |
| てくてく歩いて行きます。 住宅街を歩いて行きますよ。 |
 |
||
| おじゃましますー |
| なだらかに下っていきますが、市役所のあるあたりは、武庫川の自然堤防の上ということだそうです。 -15:40- 途中、伊和志津神社に寄ります。 |
 |
||
| 伊和志津神社 |
| 伊和志津神社は延喜式神名帳で既に大社に列格しているため、創建は遅くとも9世紀以前という宝塚随一の古社になります。 ここに、1995年(平成7年)に都市計画道路が通ったのですが、交差する参道は立体交差化し、拝殿等が新築されました。 参道が道路でぶった切られることのなかった好例として紹介されましたよ。 |
 |
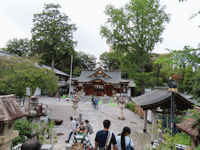 |
|
| 参道が階段状で道と交差 | 拝殿 |
| ということで先に進みます。 塩尾寺参道入口を通っていきます。 こんなところから参道なんだという場所に道標がありました。 地元の人でもあまり知らないだろうなぁ。 宝塚カトリック教会そばの、阪急電車の踏切のところにやってきました。 電車からはよくみていたけど、直近でじっくり見るのは初めてですねー。 しばし、撮影タイムです。 |
 |
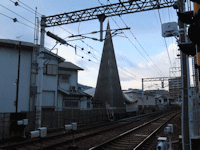 |
 |
| おー | いいねー | 尖塔が目を引きます |
 |
 |
 |
| 避雷針にもなっているらしい | 移動し始めたら踏切鳴った | ということで踏切待ちに撮る |
| 阪急電車とのコラボで獲ってみたり。 |
 |
 |
|
| うまく撮れない | 《クリックで動画再生》 上手く撮れないので動画にしてみたり |
| では踏切渡って教会に向かいます。 |
 |
||
| 狭い通路を進む |
| -16:00- 「カトリック宝塚教会」にやってきました。 |
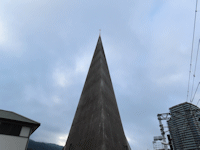 |
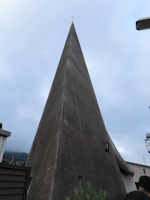 |
|
| 質感がすごいなぁ | おー |
| 窓があまりないですね。 |
 |
 |
 |
| 小窓がいくつか | 線路沿い | 出っ張った小窓 |
 |
 |
 |
| 明り取りかなぁ天井際に窓 | 地面から生えている用にも見える | 何とも言えない曲線美 |
| 曲線の屋根の端部は尻尾のように出ていました。 |
 |
 |
|
| 端部 | 教会入口 |
| まずは外部で笠原先生のお話し。 この教会の平面は、二等辺三角形なのだそうです。 しかし、外観からはそのような感じはないですね。 二等辺三角形を感じさせない不規則な感じがありますが、それを感じさせるようにつくるのはモダニズムになります。 カトリック宝塚教会は、1965年(昭和40年)に建設されました。 村野藤吾は、1960年代からは自由なデザインになっていったということだそうです。それまではモダニズム寄りな設計をしていたそうです。 1960年代は村野藤吾が70歳代で、その年齢になってもなお変化し続けるというのは驚異的ですね。 村野藤吾は、1984年(昭和59年)に93歳で亡くなりますが、亡くなる前日まで仕事をしていたそうです。 カトリック宝塚教会の設計は1963年(昭和38年)、この次に設計したのが、大阪・梅田の換気塔だそうです。 地下街・ホワイティうめだの換気をしていますね。 その後は、箱根樹木園休息所や小諸市立小山敬三美術館などが、なかなかな自由さを誇るデザインとなっているようで、晩年を迎えます。 |
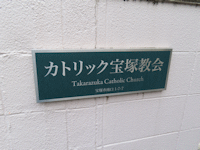 |
 |
 |
| カトリック宝塚協会 | 二等辺三角形底辺部から | 教会入口あたり |
 |
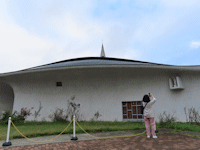 |
 |
| マリア像? | 曲線がすごいなぁ | 《misenさん撮影》 窓も複雑 |
| 外観は市役所でレクチャーを受けたようにハイヒールを逆さにしたようなデザインですね。 また、村野藤吾自身が「大洋を漂いつづけていた白鯨がようやく安住の地をみつけ岸辺に打ち寄せられたとでも申しましょうか。」と語ったように、白鯨とも見えます。 「白鯨」と言えば、ハーマン・メルヴィルの小説を元にした映画などで知られますが、旧約聖書には白鯨の話があるそうです。
ということだそうです。 間違を選んでしまった時、悔い改めてもう一度やり直なおすことができる。 ということの話のようですね。 村野藤吾は竣工時「建物が地面に建っているというより、『はえ』ているようにしたいと思った」と語っていて、その言葉通り、モルタル吹き付けの白壁は地面から生えているようです。 |
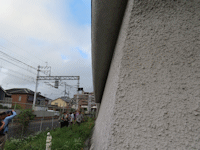 |
 |
 |
| 壁 | 電車来た | 地面から生えているよう |
| 壁でのっぺりしそうなものですが、曲線で構成されているのでそんな感じはまったくないですね。 |
 |
 |
 |
| すごいなぁ | 《misenさん撮影》 いいねー |
尖塔には換気口かな? |
| 建築家・ル・コルビュジェのロンシャンの礼拝堂をも連想させます。 入口の形状とか、屋根の形状とか。 |
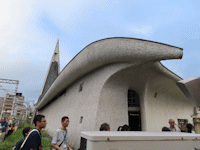 |
 |
|
| ハイヒール逆さというのもわかるデザイン | 《Googleストリートビュー》 ロンシャンの礼拝堂 |
| 樋がないですが、屋根で受けた雨水は、当初は入口横の屋根の端部に集められ、そのまま地面に落ちていたそうですが、すぐ隣の建物を建てた際に、落ちる雨水がはねて壁を汚すとのことで、雨水を受けるモニュメントのようなものが後付けで設置されています。 |
 |
 |
 |
| 内樋みたいにはなっている感じ | モニュメントで受ける | 《misenさん撮影》 施工大変だっただろうなぁ |
| 中に入ります。 外観からは想像できない空間が広がっていました。 |
 |
 |
 |
| 天井のうねりがすごい | おおおー | こちらにも出入口がある |
| 教会の椅子は長椅子が多いそうですが、ここは個人として座る椅子です。 そして、村野藤吾デザイン。 |
 |
 |
|
| ステキ | 厚みと角度のある背もたれ |
| 向かって左側は阪急電車がすぐそばを走るので、音の問題もあってほぼ壁。しかし、上部には窓を設置して明かりをとり、柱により連続性を見せています。 レンガ積みの壁は実は斜めになっていて、高度な積み方となっています。 向かって右側の壁は、斜めに配置された壁が重なるようになっていて、その間に縦窓があるような形になっています。 二等辺三角形の平面のはずなのに、どこを見ても左右非対称となっています。 ステンドグラスに見えるのは、墨色を基調にしたガラスレリーフのようなものでステンドグラス作家・作野旦平によるものだそうです。 竣工当時はガラス工芸家・岩田藤七によるステンドグラスだったそうですが、茶褐色で暗すぎたとのことで、12年後に取り換えられたのだとか。 明り取り窓に使われているのはブロックですが、工業製品を使うというのも数寄屋のひとつのやり方ということでした。 ここで、信徒であり事務局側の方から宗教的な話も含めお話しをしていただきました。 キリスト教では、宗派がいろいろあって、よく聞くのは カトリックとプロテスタント。 カトリックの三種の神器とも言えるのは、イエス・キリスト、祭壇、聖櫃だそうです。 カトリックでは十字架にはキリストが張り付けられていますが、プロテスタントでは十字架だけだそうです。 教会によってイエスはいろいろで、血みどろのイエスがおられる教会もあるそうです。 ちなみに、カトリックは神父で、プロテスタントは牧師と言いますね。 それぞれの宗派で違いがあります。 祭壇は、キリストの「最後の晩餐」の食卓を模したそうで、パン(御聖体)をイエスが最後の晩餐で弟子たちに「これはわたしの体である」と言った言葉に基づき、信者が霊的な糧として祭礼でいただくそうです。 聖櫃はミサで聖別されたパン(御聖体)を保管する箱状の容器で、イエスが実体として現存する場所を示す最も大切な聖堂の一つだそうです。 聖櫃のそばには、キリストの臨在を表す赤いランプが常時灯され、信徒はそこへ祈りを捧げるとのことです。 インディ・ジョーンズの映画「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」がありましたが、この聖櫃は、旧約聖書に登場する「契約の箱」で、モーセが神から授かった十戒が刻まれた石板が納められ、イスラエルの民の神聖な遺物とされるものなので、カトリック教会にある聖櫃とはちょっとい違いますね。ユダヤ教が示す聖櫃です。 内部を自由見学です。 祭壇には上がらないようにとのことです。 |
 |
 |
|
| コンクリートブロックを使用 | 照明 |
| 向かって右側の壁の縦窓は、祭壇側から見るとわかります。 |
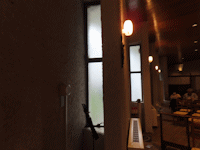 |
||
| 間接照明ぽくしているということか |
| 祭壇あたりから参列者席のほうをみてみます。 |
 |
||
| 結構広い |
| 祭壇まわりを拝見します。 |
 |
 |
 |
| 天井の曲線がすごい | 聖櫃 ランプ点灯中 | 《misenさん撮影》 作野旦平のガラス |
| 宝塚市役所の宝塚料理店を紹介した「華麗なる建築」の紹介を事務局さんがされていました。 |
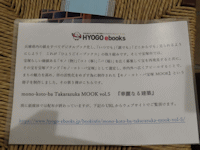 |
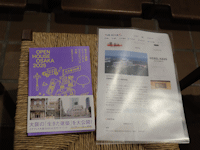 |
|
| 「華麗なる建築」 | 昨夜の「新美の巨人」とか |
| 最前列の祈祷台も村野藤吾のデザインだそうです。 |
 |
 |
|
| 跪く台 | 村野デザインらしい形 |
| 小聖堂でしょうか。カーテンで仕切られた礼拝場所がありました。 |
 |
 |
|
| 位置的には後方右手 | カーテンで仕切られます |
| 後方左手はマリア像とかありますね。 |
 |
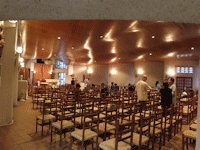 |
|
| 何の棚かなぁ | 小規模ながらすごいです |
| 2階に上がってみましょう。 |
 |
 |
|
| 階段 | ちゃんと1段目は浮いている |
 |
 |
|
| 手摺も美しい | 《misenさん撮影》 いいですねー |
| 2階は聖歌隊席になっています。 |
 |
 |
|
| 聖歌隊目線 | 天井は下から観るほうがいいね |
| 2階も細部にわたり凝っています。 |
 |
 |
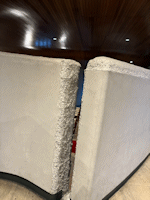 |
| 手摺 | 内側に控えた窓 | 《misenさん撮影》 腰壁はスリット入れて切っている |
| 狭い空間でも窮屈さを感じさせない納まりになっていますね。 降りていきますか。 |
 |
 |
 |
| 階段 | 手摺の曲線 | 途中の滑り出し窓 |
| 階段裏も観ておきましょう。 |
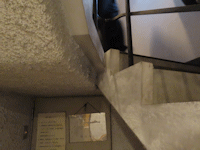 |
 |
|
| 複雑な納まり | 丁寧な仕事だなぁ |
| 椅子は、50年前の木製椅子とは思えないほどしっかりしていますね。 |
 |
 |
 |
| すごいなぁ | しっかりしている | 床タイルはオリジナルのままなのかな |
| 向かって左の斜めの壁もじっくり観ておきましょう。 |
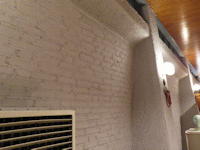 |
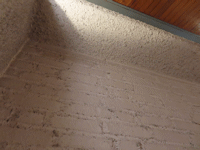 |
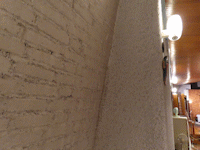 |
| 撮り方悪いので壁が垂直に見える | 上部 | 正しい角度 |
 |
 |
|
| 《misenさん撮影》 2階も斜めになっています |
《misenさん撮影》 この家具も村野藤吾かな |
| あと、教会を維持していくのにご寄付をということなので、心ばかりですがしておきました。 最後にアンケートを記入して解散です。 いやぁ。楽しかったなぁ。 ありがとうございましたー。 またこういう機会があれば参加してみたいですね。 最寄りの阪急・宝塚南口駅に向かいます。 |
 |
 |
|
| 阪急電車の下をくぐる | よくこんな通路とれたな |
| てくてく歩いて行きます。 -17:00- 阪急・宝塚南口駅から電車に乗ります。 |
 |
||
| 西宮北口行き |
| -17:15- 阪急・小林駅で降りて、てくてく帰ります。 一旦帰宅して、汗だくなので着替えよう。 -18:00- ご近所の、「TRATTORIA SCAMMARO」さんにやってきました。 |
 |
||
| お久しぶりー |
| いやぁ。久しぶりですねー。 アラカルトでいただきますよ。 |
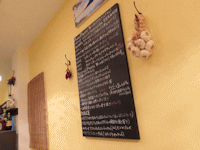 |
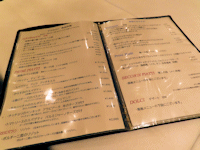 |
|
| 黒板メニュー | 定番メニュー |
| お誕生日祝いですし、阿波のワインをボトルで行きましょう。 |
 |
||
| 18:10 Janare Falanghina Del Sannio Guardia Sanframondi Spumante Brut Metodo Classico |
| おー。ファランギーナ種のワインはやっぱり美味しいなぁ。 食も進みそうですね。 |
 |
 |
|
| アンチョビとバターのブルスケッタ | イワシのマリネ |
| 今日はほぼ満席となるようです。 |
 |
||
| 予約しておいてよかった |
| というわけで、スパークリングワインは早々に空いてしまいましたので、グラスワインにいきますか。 |
 |
||
| 18:37 Quid Falanghina Spumante Brut |
| そして食べていきます。 |
 |
||
| 太刀魚と茄子のフリット |
| いやぁ。美味しい。 |
 |
||
| 18:46 Il Vei Emilia Bianco |
| そして食べます。 |
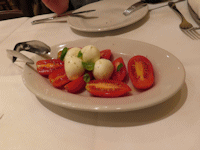 |
||
| カプリ風サラダ |
| 飲んじゃいます。 |
 |
 |
 |
| 18:59 Pietra dell'Orlo Greco di Tufo DOCG |
19:07 Giovanni Molettieri Campania Rosato ロゼです |
19:20 Janare Aglianico 安定のアリアニコ |
| いやぁ。楽しいですねー。 PrrimiとSecondiがもういっしょになってくる楽しさですよ。 ・・・美味しいので、ついつい頼んじゃうので、お作法通りにだいたい進みません(笑) |
 |
||
| 太刀魚と茄子、トマトの香草パン粉焼き |
| いやぁ。水のようにワイン飲んでいましたね。 だって美味しいんだもの。 |
 |
||
| 19:41 Toscana Sangiovese Fattoria La Lecciaia |
| このワイン、長期熟成されていて、10年熟成を経てリリースされているものです。 |
 |
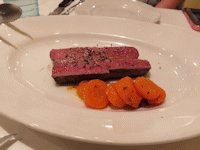 |
|
| 4種のチーズのパスタヴェスヴィオ | 岐阜県産シカロースの炭火焼 |
| 最後にもう1杯。 |
 |
||
| 20:09 Edizione Privata Torre Giacomo |
| これ、3種類の品種のブレンドワインです。 美味しい! そしてドルチェです。 |
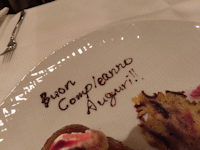 |
 |
|
| misenさんおめでとうー | 美味しゅうございました |
| そして、ババとか田舎パンとかテイクアウトして帰りましたよ。 いやぁ。いつもながら大満足でした。 地元のことながら、知らないこともまだまだありますね。 人生のうちで、全てを知ることは無理でしょうけど、少なくとも興味があることは、知れる機会があれば知っておきたいなぁ。 久々に、休日らしい1日でした。 |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.