 |
 |
|
| 小林駅 | お客はほぼゼロ |
RockzGoodsRoom > Outing > Outing2025 >
RockzGoodsRoom > Goods >
| 2月 「草屋根の会」の代表の建築家・前田由利さんが、以前から岩手の芝棟を観に行きたいと言っておられました。 「芝棟」とは、茅葺き屋根の棟に芝の生えた土を置いて、棟の固めとしたもので、「くれぐし」とも呼ばれます。 茅を葺いていくと、一番上は蓋をしないと雨漏りになります。 現代の茅葺屋根でよく見るのが、杉皮か代用品としてトタン板を被せて、それが風で飛ばないように留める工夫が、地域によって違っていたりして風情があります。 恐らくそれ以前にポピュラーだったのは、芝棟をつくることで芝土に生い茂る植物が根を張り棟を固定し、風雨への抗力を高める棟仕舞のひとつの手法であったのだろうと思います。 かつては広く行われていたと推察されていて、戦前までは東北から九州にかけ、特に東日本で多くみられたようですが、1960年代以降、茅葺き屋根の消失とともに急速に姿を消しました。 今では100棟もないようですね。 そういえば、以前行った、建築家・藤森照信先生の手掛けた、「ねむの木こども美術館」にも芝棟がありましたね。(こちら) 藤森先生は言います。「建築と植物は視覚の面で相いれないもの。その唯一に近い例外が芝棟だ。」 芝棟は日本だけかと言うとそうではなく、ユーラシア大陸の北半分には広く分布しているそうです。 今年は行きましょう!ということで、6月に行くことが決まりました。 その後、事務局中心にスケジュールを考えたり。 結構タイトですが、青森空港に降り立ち、紫波町のオガールに泊まり、建築や芝棟を見ながら、いわて花巻空港から帰るという1泊スケジュールで行くことになりました。 2月17日 早速、行き帰りの飛行機を取ろう。 朝一番、青森に行き、翌日夕方にいわて花巻空港から帰るとなると、乗れる便はほぼ一択です。 これまでは、できるだけANAが好きなのでANAに乗るようにしていましたが、今回はJALですねー。 そして、座席数が少ない。 早く取っておくに越したことはないですね。 行の青森便は、早割で取るとなぜか1クラス上のクラスJのほうが一般座席より安いので、そちらで取りましたよ。 5月13日 事務局から、参加メンバーと最終なスケジュールが発表されました。 青森県立美術館、ちょうど、特別展で「描く人、安彦良和」を開催していますね。 これ、昨年6月から9月の兵庫県立美術館で開催していたのですが、なんやかんや忙しくて行けず。 せめて、図録だけでも欲しいなぁと思っていたのです。時間あれば見られるかなぁ。 今回、新たにJALのアプリを入れたのですが、ある時から接続ができなくなりました。 ログインできないって・・・・。 仕方がないので、メールからGoogleウォレットに登録して使えるように。 JALアプリ、アンインストールしよう。 前日、飲み会も入れず、早目に帰宅して準備して眠ります。 明日、明後日はいい天気だといいなぁ。 ところで、東北の今は気温どうなのだろう。 一応、上着も持て行っておくか。 6月7日(第1日) -04:30- 目覚めます。 眠いな。 準備します。 -05:00- では行きますか。 今回は機内預けの荷物にはせず、バックパックで行きますよ。 てくてく歩いて、最寄りの阪急・小林駅へ。 この時間でも、もう空は明るい季節なんですね。 -05:15- 阪急・小林駅にやってきました。 |
 |
 |
|
| 小林駅 | お客はほぼゼロ |
| -05:30- 宝塚方面行の電車がやってきました。 |
 |
||
| 乗りますよー |
| -05:40- 阪急・宝塚駅で大阪梅田方面に乗換です。 |
 |
||
| 宝塚線 |
| -06:05- 阪急・蛍池駅で大阪モノレールに乗り換えます。 予定より1本早いモノレールに乗れました。 しかし、ラッシュだな。 -06:15- 大阪モノレール・大阪空港駅で降ります。 |
 |
||
| 空港へ向かう |
| 今日は超久しぶりに北ターミナルです。 JALに乗るのも何年ぶりかなぁ。 2012年に神戸空港から沖縄に飛んだ時以来かなぁ。 混むと嫌なので、さっさと保安をパスしますが、あら?モノレールの混雑からもっと混んでいると思ったのに、ほぼならばず入れました。 発着便数から言うと、ANAよりJALのほうが多いので、ANAに向かう人のほうが多かった。というのも考えにくいなぁ。 水筒を出していたので、保安では当然別レーンに荷物が行きます。 中身飲んで確認でOK。 24Aゲートのようですね。 かなり端だな。 |
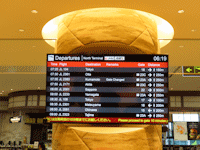 |
||
| 海外に行くよな雰囲気 |
| サンドイッチ買っていこう。 てくてく歩いて24Aゲートへ。 |
 |
 |
|
| 遠いです | JALいっぱい |
| 24Aゲートに到着し、待合で席を確保します。 朝ごはんでサンドイッチ食べますよ。 |
 |
||
| 朝空港に来たらだいたいこのサンドイッチ食べています |
| 出雲便の待ち客が多い模様。 その次が青森便ですね。 |
 |
||
| ボーディングブリッジ通るかな |
| 出雲便の搭乗開始で、団体のご老人たちがゲートを通過。 しばらくすると、おひとり戻ってきました。 どうやら待合の席に荷物を置き忘れたとのこと。 団体の他の方がまだゲートを通っていなかったので、無事荷物も回収できたようです。 出雲便の客が減ると、おー、今回参加の皆さんと合流。 -07:10- 青森行搭乗開始です。 最後に乗り込むGroup4なので待ちますよ。 |
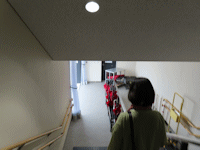 |
||
| 階段を下りていく |
| さて、乗りますか。 階段を下りて、滑走路に出ててくてく歩きます。 |
 |
 |
|
| エンブラエル190 | JALグループのJ-AIRだらけ |
| タラップで乗り込みますよ。 |
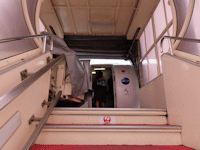 |
||
| 空への階段 |
| 行に乗るのは、エンブラエル190です。 ブラジル・エンブラエル社が製造する小型ジェット旅客機ですよ。 帰りもエンブラエルに乗りますが、170。 170と190はぱっと見同じなんですけど、190のほうが少し大きいです。 標準座席数は104席ですが、このJAL(J-AIR)15席のクラスJと80席の普通席を設定して95席となっています。 このクラスJは、国内線向けのミドルクラスの座席です。 グッドデザイン賞を受賞した、平均47cmと普通席に比べて幅の広い座面と肘置き、フットレストと引き出し型テーブルを持っているようですね。 ANA2151便のクラスJシートは、右に2列、左に1列の配置で、左の1列の席を予約していました。 |
 |
||
| 右2列のクラスJ |
| -07:15- 扉が閉まりました。 |
 |
 |
|
| 乗り込みました | タラップ外れます |
| カップホルダーが左の肘掛下にありました。 テーブルがないなぁ。 |
 |
 |
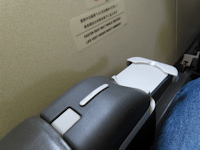 |
| 一般席は正面位t−ブルがあるんだけどなぁ | カップホルダー | ここにあった |
| 押してバックさせていたトーイングカーが外れ退避し、グランドハンドリングクルーの皆さんが手を振ってお見送りしてくれます。 こちらからも手を振り返しておこう。 |
 |
 |
 |
| 押されてバックしています | 退避 | いってきまーす |
| タキシングします。 |
 |
 |
 |
| 滑走路へ | 飛行機たくさん | 渋滞していますな |
| 離着陸のラッシュアワーで、離陸待ちの列になります。 機内誌でも読むか。 ANAの「翼の王国」は完全デジタルになっていましたが、JALの「SKYWARD」はまだ紙媒体でした。 |
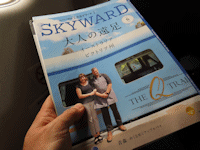 |
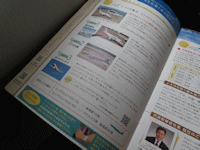 |
|
| SKY WORD | エンブラエル170と190の違い記事 |
| 実際には170と190は同じ機体ではないのですが、確かにぱっと見同じですからね。 おもしろい記事でした。 -07:40- ようやく離陸します。 いつもは右側に座りますが、今日は1列シートめがけて左側に座りましたので、久しぶりに昆陽池の日本列島が見えました。 |
 |
 |
 |
| 《クリックで動画再生》 "Danger Zone"Kenny Loggins 離陸です |
昆陽池の日本列島 | 伊丹空港と園田競馬場 |
 |
 |
 |
| 伊丹空港は飛行機だらけ | 淀の京都競馬場 | 琵琶湖だ |
| いつもは右に座るので、左側の景色も面白いですね。 |
 |
||
| 栗東のJRAトレーニングセンター |
| 雲が多いですね。 |
 |
||
| 雲の上 |
| 冠雪している山が見えました。 |
 |
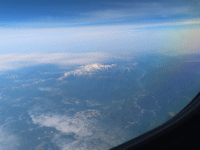 |
|
| 雪が残っているのは白山ですかね | 右側は御母衣湖かな |
| 機内サービスでドリンクがいただけました。 ホットコーヒーにしよう。 テーブルは、右の肘置下に収納されていて、CAさんが出してくださいました。 |
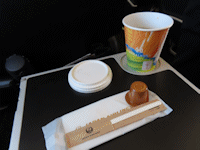 |
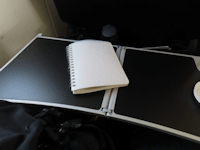 |
|
| おー | 広げられます |
| 関東の方に進んでから北上するのかと思っていたのですが、富山湾付近をかすめ洋上へ。 |
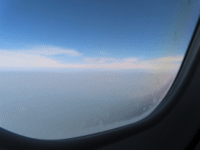 |
||
| 雲が多い |
| 雲が多く佐渡島は見えませんでしたが、再び陸地が見えた時は男鹿半島でした。 |
 |
||
| 大潟村の八郎潟の干拓だな |
| 最終アプローチです。 一旦、青森市街地上空でターンします。 |
 |
 |
 |
| アスパムと八甲田丸 | 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 | 陸奥湾から津軽半島のほう |
| そして空港への進入ルートへ。 |
 |
||
| 八甲田山かな |
| -08:55- 北から進入して、青森空港に着陸しました。 |
 |
 |
|
| 《クリックで動画再生》 "Mighty Wings"Cheap Trick 着陸です |
5年ぶりの青森空港 |
| ボーディングブリッジが繋がれます。 |
 |
||
| 降りるのは楽だな |
| 約10分遅れで降ります。 |
 |
||
| 降りますよ |
| 手荷物受取を素通りし、自動ドアを出ると、バスの運転手さんんがプラカード持ってお待ちいただいていました。 よろしくお願いしますー。 では、青森空港集合組は全員揃ったので、バスに乗り込みます。 |
 |
||
| 新栄観光さん お世話になりますー |
| 岩手県遠野市の観光会社で運転手さんは朝5時半に出発してここまで来られたそうです。 ありがとうございますー。 -09:10- 出発します。 |
 |
||
| お花植えています |
| 県道27号を北上します。 県道44号を北上し、東北新幹線をくぐります。 市道を走り、東北道をくぐりR7へ。 |
 |
||
| 東北道です |
| そして市道に入ります。 一旦、青森県立美術館前の駐車場に。 事務局で先に青森県立美術館の入場券を購入します。 今回は15名参加なので団体料金は適応できませんが、青森県立美術館の当日有効のチケットがあると団体料金になるので先にチケット購入と言うことです。 購入後、バスで移動します。 -09:50- 「三内丸山遺跡」にやってきました。 |
 |
||
| 地層模様だ |
| こちらの「縄文時遊館」は2002年(平成14年)に竣工した、梓設計の設計ですね。 周辺と同化させるため、建物全体を土と緑で覆うことで地形と馴染むよう計画し、年間を通じ安定した地熱や雨水といった自然エネルギーを最大限に活用することで、環境負荷の低減をめざしています。とのこと。 |
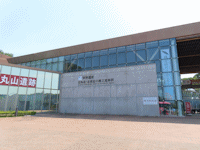 |
||
| 世界遺産ですよ |
| 前田さんのご挨拶で今回のツアースタートです。 |
 |
||
| ご挨拶 |
| まずは、約3時間の予定で、こちらの「三内丸山遺跡」と「青森県立美術館」の見学を、昼食含めてでお願いしますとのことです。 では早速活動開始です。 |
 |
||
| 両施設のチケット |
| 縄文時遊館に入口があります。 10時半にボランティアガイドがありますね。所要時間は約50分。 それに参加してみますか。 それまで「さんまるミュージアム」を観て、15分ほど縄文シアターで観て、ボランティアガイドに参加しましょう。 「さんまるミュージアム」に入ります。 |
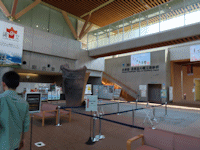 |
 |
 |
| エントランス | ガイド集合場所 | さんまるミュージアムに行きます |
| 展示は少ないのかなと思ったら、意外と広々、いろいろありますね。 |
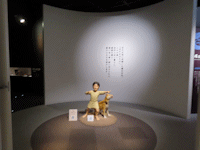 |
 |
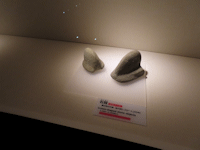 |
| 縄文人の子供に導かれる | 縄文土器 | 石冠 エルゴノミクスなマウスに似ている |
| 石冠は、その名の通り冠のような形をした石製品です。 用途は不明ですが、祭祀用具と考えられています。 |
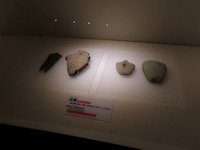 |
 |
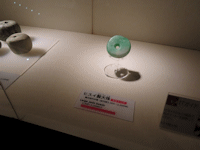 |
| 岩偶 | 土偶 | ヒスイ製大珠 |
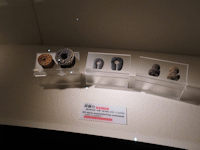 |
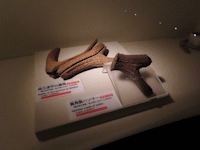 |
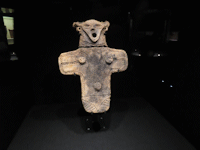 |
| 耳飾り | 鹿角製ハンマー | 大型板状土偶 |
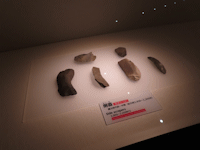 |
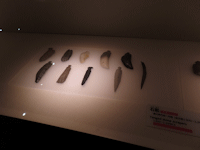 |
 |
| 削器 | 石匙 | 石鏃 水晶製のもある |
| すごいですねー。見る物すべて重要文化財。 |
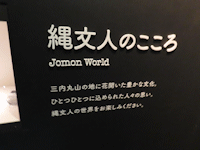 |
||
| 縄文人のこころです |
| 子供の頃に教科書で習った縄文人は、狩猟民族で安定した暮らしができず、文化度もそう高くなかったと思っていたのですが、現代人よりも高度な細工とかもしていますね。 |
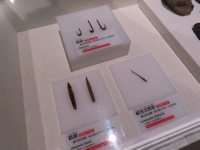 |
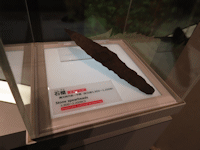 |
 |
| 釣針や銛頭 | 石槍 | 石鏃=矢じり |
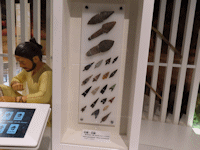 |
 |
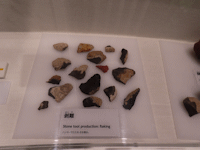 |
| 石槍・石鏃がたくさん | 原石を用意し | ハンマーで叩き剥離 |
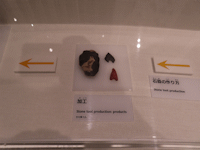 |
 |
|
| 形を整えます | 完成! |
| 地層が見られます。 |
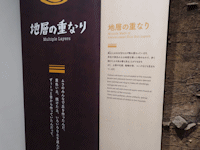 |
 |
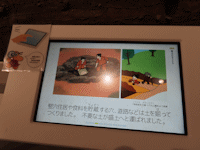 |
| 解説 | 人が土を重ねて陸を作ったそうです | 造成の切り盛りってとこか |
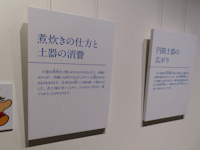 |
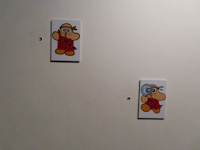 |
|
| 土器は消耗品 | 穴から向こうが見えます |
| いろいろあります。 |
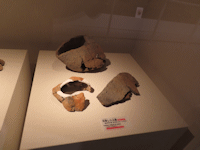 |
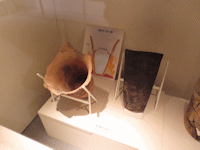 |
|
| 失敗した土器 | 煮炊きの跡 |
| 縄文人も失敗したものを子孫に見られたくなかったろうなぁ。 |
 |
||
| 土偶いっぱい |
| 縄文人はニワトコの種子で酒造りをしていたのでは?と考えられているようです。 |
 |
||
| ダンブルドアの杖ではない |
| 多くの土器がありますね。 これだけ出土するのはすごいなぁ。 |
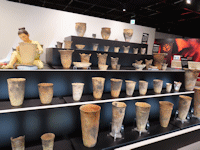 |
 |
|
| うわぁ | 時代により変化している |
| 土偶は縄文時代特有のものです。 弥生時代になると姿を消します。 |
 |
||
| 土偶もいっぱいあります |
| 土偶なのか、木製の神仏なのか、このあたりは、縄文人と弥生人の文化の違いなんでしょうね。 すなわち、縄文人が弥生人に発展したのではないという通説が正しいのかなというところです。 ただ、これも最近違うようで、縄文人、弥生人だけで分けられるものではなく、琉球、本土、北海道の3つの異なる文化系統でゲノム解析では違いがあるそうです。 旧石器時代に日本列島へ流入してきたルートとして考えられるのは主に3つ。 朝鮮半島から対馬を経由してくるルート、台湾から琉球列島を渡るルート、シベリアから北海道を通るルートです。 そのため縄文人と言ってもその時代に単一民族であったかも不明で、現代日本人のルーツが、縄文人か弥生人かで分けられなくなっているそうです。 |
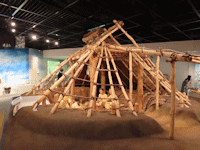 |
||
| 住居復元模型 |
| アクセサリー(と思われている)ものも多くあります。 |
 |
 |
|
| 土製ペンダント | 石製ペンダント |
| 縄文服がありました。出土したソ座不明の編み物をもとに、土偶の模様を参考にして創作したものだそうです。 |
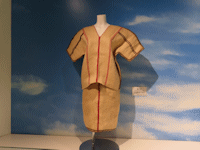 |
||
| ほほう |
| 子供の墓がありました。 |
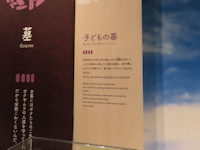 |
 |
|
| 解説 | 棺代わりに普段使っていた土器 |
| お墓は道沿いに並んでいたそうです。 |
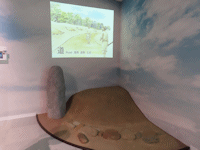 |
||
| お墓の続く道 |
| 紀元前でも既に交易はしていたようですね。 |
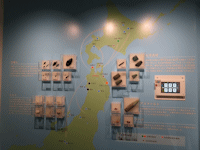 |
||
| どこのものか判明しているらしい |
| 江戸時代から存在が知られていた三内円山遺跡ですが、大規模な発掘調査は、1992年(平成4年)からだそうです。 |
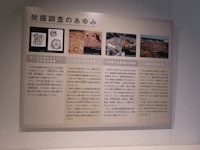 |
||
| 県営野球場建設が発端 |
| 「さんまるミュージアム」終了です。 |
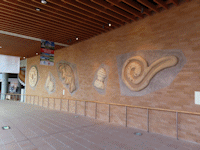 |
||
| 壁のオブジェ |
| 10時半からのガイドツアーまで少し時間があります。 縄文シアターで10時20分から8分間の「三内円山遺跡センターガイド映像」が見れますね。 ということで拝見。 -10:30- ガイドツアーに参加します。 |
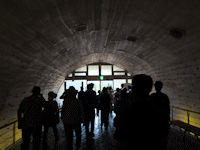 |
||
| 時遊トンネルをくぐり5,000年前へ |
| よろしくお願いしますー。 |
 |
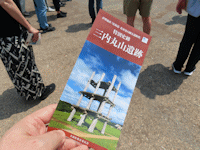 |
|
| ガイドさん | パンフレット |
| この、三内丸山遺跡は、江戸時代から遺跡があることは知られていたようですが、1992年(平成4年)に新しい県営野球場を建設するための事前調査を行ったところ、大規模な集落跡が見つかり、また6本柱跡も見つかったことから、県営野球場のお建設は中止し、遺跡を保存することになりました。 2021年(令和3年)には、「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界文化遺産に登録され丸4年になろうとしています。 環状配石墓があります。 今、見ているのは復元ですが、道沿いに24基が見つかったそうです。 道路の形態も、370m発掘されたそうです。 |
 |
 |
 |
| 環状配石墓 | 解説 | 道路跡 |
| 遠くに芝棟と大型の掘立建物が見えますね。 |
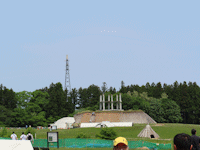 |
||
| 重なってちょっと変 |
| その向こうの鉄塔の先端が黄色く塗られています。 なんで黄色いのだろうと気になったので調べてみると、ヘリ巡視(ヘリコプターによる、送電線の点検)の際の目印となっているのだそうです。 電力会社により規定はまちまちだそうですけどね。 今の道路跡の舗装は、ニセアカシアを伐採した際の材木のチップだそうで、過去がこうだったというわけではないです。 |
 |
||
| 木材チップ舗装 |
| 改めて、三内丸山遺跡の紹介です。 |
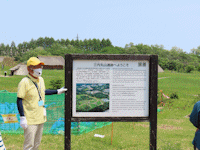 |
||
| 看板 |
| 三内丸山遺跡の広さは42haあり、東京ドーム9つ分あるそうです。 この地は紀元前3,900年〜2,200年の約1,700年間にわたり人が定着していたと考えられています。 2年間の発掘により出土したものは、現時点で引っ越し段ボールで約4万個分。 その中には、土偶が2,000戸、土器は6,000個復元されていますが、土器は破片で出てくるので、それをパズルのように組み合わせ復元していくのですが、まだ10億個の破片があるのだとか。 全てを復元することは難しいでしょうけど、それでも気の遠くなる作業ですね。 建物の跡も600ほど見つかっています。それでも、発掘調査は全体の4割ほどしか進んでいないとのことです。 |
 |
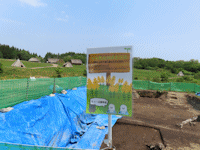 |
|
| 今年の発掘 | 来月から公開なのですね |
| 三内丸山遺跡の人口はどうだったのか。 この推測は学者でも難しいそうです。 600ほどの建物は全てが住居と言うわけではなく、倉庫などもあったと考えられています。 100戸ぐらいが住居だったのではと考えられ、当時の平均寿命が30歳代で、一戸あたり5人家族としても、500人くらいだったのではということです。 |
 |
||
| 芝棟のある建物 |
| 復元した建物が建つ場所は、実際に発掘した場所ですが、上屋は何も残っていないので、東南アジアの建物を参考とした推測の建物だそうです。 |
 |
 |
 |
| 広いですねー | 住宅がいっぱい | いろいろなスタイルがある |
| 大型の屋根葺き替えは大変でしょうね。 |
 |
 |
 |
| 人力だけでやっている | こちらは南盛土 | 八甲田山が少し見えます |
| 南盛土は、建物を建てた際の土の捨て場だったようです。 発掘すると、遺品が多く出土しています。 5,000年ほど前の土だそうですよ。 |
 |
||
| 解説 |
| 調査では、深さ1.8mのトレンチを掘ったそうですが、それでわかったのは約1,000年捨て続けた土の層となっていたそうです。10世紀分かぁ。 |
 |
 |
 |
| ということで地層を見ます | おー | 土器やらいっぱい出ている |
| 竪穴住居跡を見ていきます。 15棟が復元されていますよ。 |
 |
 |
|
| いろいろなタイプ | 地面と一体化した土屋根 |
| 掘立柱建物跡もあります。 |
 |
 |
 |
| 復元されています | 掘立柱跡 | 高床式と推測されています |
| 大人の墓は、膝を曲げて埋葬される屈葬式だったようで、 直立で寝る状態ならもう少し大きい墓になるでしょうねということです。 棺に入れず土葬ににするのが普通だったようです。埋葬品には土器や矢じりなどがあるそうですが、どれも男女の別は不明なんだそうです。 |
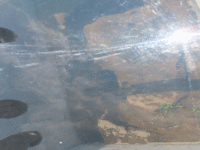 |
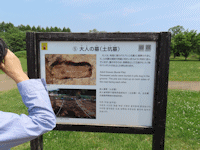 |
|
| 墓跡 | 解説 |
| 当時から他の地域と交流があったようで、翡翠のペンダント(かどうかはわからないですが現代人がそう判断しているもの)は、新潟県糸魚川沿いのものであると判明しているそうです。 人骨はどの墓からも出てこなかったそうです。 地層には、火山灰の層もあったそうで、これは、実は十和田湖がカルデラ湖であるのですが、その噴火によるものだそうです。 火山灰は酸性が強いためそれで人骨が無くなったのではという学者の考えがあるそうです。 墓は道沿いに続いていますが、420m先までは確認できていますが、その先は既に遺跡として保存されていない土地になっているようですね。 |
 |
||
| この先両側に墓跡 |
| 大人の墓は、470基ほど見つかったそうです。 掘立柱建物を見ていきます。 |
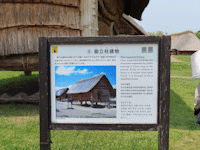 |
 |
 |
| 解説 | 壁も茅 | 芝棟がかわいい |
| 北の谷では、動物の骨が多数出土しています。まぁ、いわゆるゴミ捨て場ですね。 人骨は無くなっていたのに、動物の骨は多くあるというのは、この谷の表層が泥炭層であり、その下にある骨は空気に触れていなかったためと考えられています。 |
 |
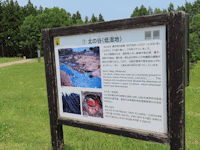 |
|
| 北の谷 | 解説 |
| 野ウサギなどの小動物の骨や魚の骨なども多く、当時どんな生き物を食べていたかがわかったそうです。 高床式の建物が、なぜ高床式であったかがわかるのかというと、住居には囲炉裏跡が見つかり、この高床式にはなかったため、地面での生活や使われ方がなかったと判断されるからだそうです。 また、床材に使われたと考えられる板材も見つかっています。 墓に近いことから、お寺や倉庫だったかもしれないとのことでした。 |
 |
||
| 倉庫か何か 芝棟かわいい |
| 北盛土に来ました。 道の下を20〜30cm掘ると土器が出てきたそうです。 |
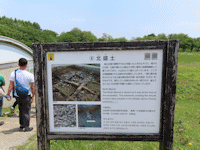 |
 |
|
| 解説 | 中に入ってみる |
| 不要になり捨てられたものではなく、それぞれに並べていて、その上にかかった土の圧力で潰れたようなものだったそうです。 儀式などで使ったものを、終った際に並べていたのではと考えられています。 |
 |
||
| ゴミ捨て場ではない |
| のどかでいいですねー。 |
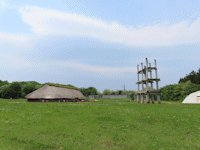 |
 |
|
| 大型竪穴住居と大型掘立柱建物 | 今見た北盛土 |
| 子供のお墓は、上屋があったようですが、老朽化のためリニューアルするそうです。 というわけで、展示物は、縄文時遊館の「さんまるミュージアム」内に一時置かれています。 |
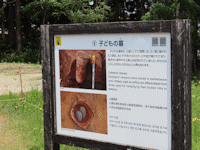 |
 |
|
| 解説 | このあたりにあった |
| 今見えている大型掘立柱建物は復元されたもので、場所も違います。 本物の建物跡は、ドーム状の建物内にあります。 |
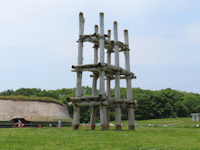 |
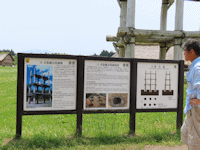 |
|
| 復元 | 解説いろいろ |
| ということで、本物の柱跡を観に行きます。 |
 |
||
| ドーム建物 |
| 直径、深さ共に2mの円形の穴が6つ見つかりました。 掘立柱があったと考えられ、根元には栗の木が残っていました。 穴は、正確に4.2mの間隔となっていて、この時代には既に長さを測る術があったようです。 |
 |
 |
|
| おー | 柱が残っているのはレプリカ |
| 出土した栗の柱の根本は、「さんまるミュージアム」内にあります。 栗の花粉も出土していて、DNA鑑定してみると、枝払い等を行っていたのがわかったそうで、人が管理する管理林だったことが判明しています。 漆塗りのお椀も出土していたことで、漆の木も管理して育て使っていたと考えられています。 柱の表面は焼いており、腐らないような処置がされていたそうです。 柱の長さは、柱の下の土の圧縮具合から計算できたそうで、約20mとのことでした。 この大型掘立柱建物が何に使われたかは不明だそうですが、北の谷で魚の骨が出土していることから、漁業もしていたと考えられ、海が遠くに見えるので、物見櫓や灯台として使われていたかも。 また建物周囲が平坦地であったので、お祭り広場の櫓だったのかもしれません。 |
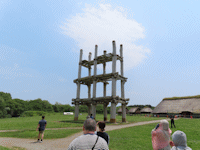 |
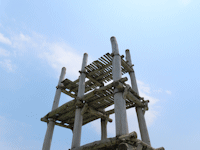 |
|
| 復元大型掘立柱建物 | これは建築物なのか工作物なのか |
| 復元の大型掘立柱建物は、高さ14.7mあります。 出土した栗の木年輪を見ると、100年は最低経過しているというのはわかったと言うことで、それくらいの樹齢の栗の木は現在の日本国内にはありませんでした。 ヨーロッパにも求めましたが見つからず、最終的にはロシア・ソチで入手したそうです。 復元には屋根がないですが、これもあったかどうかは不明です。 3層構造になっていますが、ころも想像でとのこと。 大型竪穴住居があります。 現在、茅葺の屋根は葺き替え中ですね。 その影響で、中も一部入られない部分ができています。 |
 |
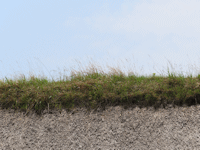 |
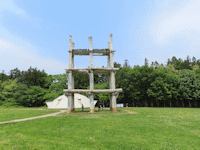 |
| 大型竪穴住居 | 芝棟 | 振り返ると大型掘立柱建物 |
 |
 |
|
| 芝棟かわいいなぁ | こちら側は葺き替え終わっていますか |
| 柱は全部で19本あり、これも栗の木です。 住居としていますが、何に使われていたかは不明で、集会所か共同作業所が考えられますが、人口規模に比して、発見された住居数が少ないことから、夏の間は外で寝ていたような人々が、冬の間の寒さに対して共同生活をしていたのかもとも考えられています。 お祭りやイベントで使われていたのかもしれませんね。 |
 |
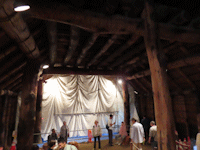 |
 |
| 中に入ります | かなり広い空間 | この時代は板材はそうなかったんだろうなぁ |
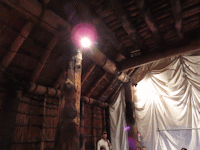 |
 |
|
| なんかすごい | 焼けてる? |
| 室内が黒いのは燻されているからで、腐食防止のためだそうです。 殺虫、防虫も兼ねているそうで、年に1〜2回は燻しているそうです。 2階の床をつくっていますが、これも想像で、雪の多い地域になるので、2階が出入口となることもあるのでは?ということだそうです。 |
 |
 |
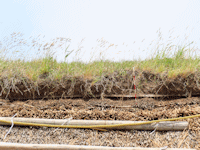 |
| 茅葺葺き替え中 | 下地見ているのも面白い | 芝棟横から |
| 長さが32m、幅が9.8m、床面積250m2もある、大型の竪穴建物は圧巻でした。 |
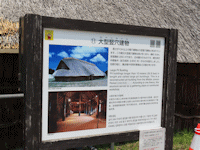 |
||
| 解説 |
| ということで約50分、詳しくガイドしていただけましたありがとうございますー。 残り時間が1時間半ないですね。 急がないと。 でも、縄文ビッグウォールを観ていないので観ていこう。 |
 |
||
| 全景が見える場所 |
| 縄文時遊館に戻り奥へ。 階段がありましたので降りていきます。 そこの壁面に5,120個もの縄文土器のかけらを約6mの高さに散りばめられている、縄文ビッグウォールがありました。 |
 |
 |
|
| これか! | おおー圧巻 |
| そしてその向かいには一般収蔵庫があります。 |
 |
 |
 |
| 大型掘立柱建物の柱 | こちらも | 出土品や復元品多数 |
| 2階には整理作業室があり、復元作業などをしていますが、今日は土曜日でお休みのようでした。 |
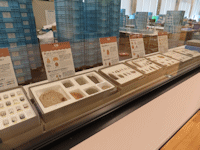 |
 |
|
| いろいろ展示 | 復元作業は今日はお休み |
| ショップも覗きました、これといってないな。 青森県立美術館に移動しましょう。 |
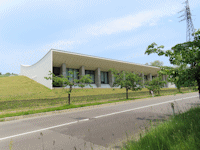 |
||
| 縄文時遊館でした |
| 前田由利さんたちと出会ったのでてくてく歩いて行きます。 いやぁ。暑いなぁ。 -11:55- 「青森県立美術館」にやってきました。 |
 |
||
| 裏から入った |
| ここも実は三内丸山遺跡と同様、遺跡があったそうですが、大規模でなかったのか、発掘調査後は埋め戻されたそうです。 2005年(平成17年)にオープンした、建築家・青木淳設計の、遺跡の発掘現場のような土の大きな溝(トレンチ)に凹凸の白い構造体を被せるという設計で、三内丸山遺跡と一体化したデザインとなっている建物です。 青木淳設計の建物は、2014年に新潟のビュー福島潟、昨年行った、京都市京セラ美術館(改修)もそうでしたね。 どうしようかなぁ。 中を観ていくか、ランチするか。 お腹すきましたねということになったので、美術館内のカフェでランチをすることに。 「4匹の猫」にやってきました。 |
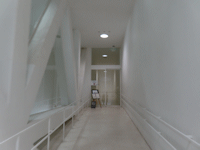 |
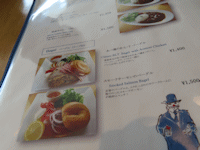 |
|
| カフェです | 何するかなー ベーグルサンドにしようか |
| あべ鶏のB・L・Tベーグルにしました。 しばし待つと来ました。 |
 |
||
| いただきますー |
| おー。いいねー。 結構食べ応えあります。 美味しくいただき、ごちそうさまでした。 ささっと美術館を観ましょう。 3回目なので、どうしても観ておきたい「あおもり犬」、あと、当初から観てみたかった、企画展「描く人、安彦良和」を追加料金支払って速攻で観ることにしました。 |
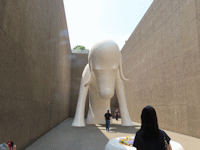 |
||
| "あおもり犬"奈良美智 |
| 1階が見えます。 |
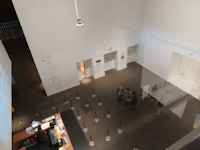 |
||
| 企画展に行こう |
| 最後に、ミュージアムショップへ。 「描く人、安彦良和」の図録を買っておこう。 |
 |
 |
|
| もう少し青空ならよかった | 駆け足だけど観られてよかった |
| さぁ。急いで戻らないと。 てくてく歩いて戻りますが、間に合うかなぁ。 |
 |
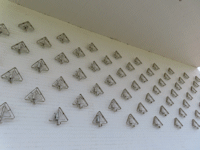 |
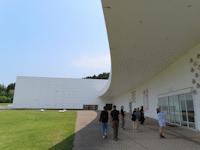 |
| また来よう | 美術館のマーク | それにしても暑いです |
| 発掘のトレンチ感がと言われれば、そうかもしれないですね。 |
 |
||
| 青森県立美術館でした |
| 少し遅れて三内丸山遺跡に戻ってきますが、大半はまだのようですね。 -13:25- 全員揃いましたので、バスに乗り込み移動です。 R7から東北道へ向かいます。 |
 |
||
| 東北新幹線をくぐる |
| -13:30- 東北道・青森ICから高速です。 |
 |
||
| 青森ー |
| 右手に見える冠雪している山はなんだろう。 |
 |
||
| 岩木山? |
| -13:55- 東北道・大鰐弘前ICで降ります。 |
 |
||
| 弘前ですよ |
| R7・弘前バイパスを走り、県道260号へ。 なんか、古民家がありますねー。 |
 |
||
| 旧石戸谷家住宅でしょうか |
| 反対側には、堀越城跡の幟がたくさん立っていました。 そして県道127号に入ります。 -14:20- 「弘前れんが倉庫美術館」にやってきました。 |
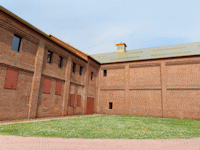 |
 |
 |
| おーいいねー | エントランス部は後から施工かな | レンガ倉庫っていいね |
 |
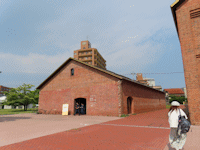 |
|
| 重厚 | 隣もレンガ倉庫 |
| 1907年(明治40年)に大工職人から日本酒の製造業に転身して事業を拡大させていた地元の実業家・福島藤助が、この地に酒造倉庫として建てた吉野町煉瓦倉庫を美術館に改修し、2020年(令和2年)に開館しました。 酒造工場として建てられ、戦後はシードル工場として使われた煉瓦造の建物を可能な限り残し、「記憶の継承」をコンセプトに建築家・田根剛が改修設計を担当しました。 エストニア国立博物館の設計(チームの一員)で頭角を現し始め、2022年(令和4年)、東京帝国ホテルの建て替え(2036年竣工予定)の建築家に選定された若手建築家です。 |
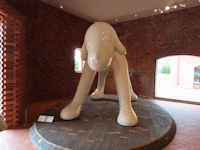 |
||
| "A to Z Memorial Dog"奈良美智 |
| 美術館の方に案内をしていただけます。 ガイド用イヤホンを装着します。 |
 |
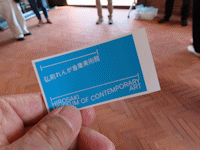 |
|
| ガイド用イヤホン | これ服に貼ってくださいねってことでした |
| では、ツアー開始です。 |
 |
||
| 1階ホール |
| まずは2階へ。 |
 |
||
| 梁むき出しに |
| この煉瓦倉庫歴史とかをいろいろお聞きします。 福島藤助は、長く残すことが可能な煉瓦造りの建物にこだわり、「仮に事業が失敗しても、これらの建物が市の将来のために遺産として役立てばよい」と語ったとされます。 |
 |
||
| 昔はここから岩手山がはっきり見えたけど今はかろうじて |
| 福島藤助は1925年(大正14年)に心臓麻痺により55歳で急逝、その後戦中の米不足もあってか酒造業は衰退し、事業経営は福島家から離れたようです。 弘前では戦中にリンゴ酒の製造が盛んになり、戦後の1953年(昭和28年)には日本酒造工業が朝日麦酒(現・アサヒビール)の後援で朝日シードルが設立されます。 |
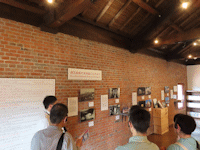 |
||
| 数奇な運命をたどります |
| 日本酒工場からシードル工場、そして倉庫になり、現在は美術館です。 |
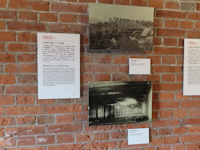 |
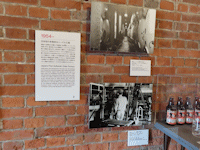 |
 |
| 日本酒工場としてスタート | シードル工場 | 奈良美智展を開催 |
| シードルを造っていた時は瓶まで国産とすることができず、フランス製の便を使用していたそうです、 |
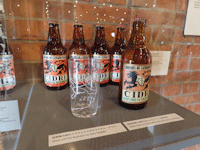 |
||
| 当時の瓶が残っていたらしい |
| しかし、シードルは当時の日本人の嗜好に合わず、ニッカウヰスキーの傍系会社となり、1960年(昭和35年)にはニッカウヰスキー弘前工場としてウイスキー製造を行いました。 1965年(昭和40年)には手狭になったことで工場移転し、日本酒造工業も吉井酒造に商号が変わり、この地での酒造工場としての稼働はなくなりました。 この後は今話題の政府備蓄米の倉庫となり1997年(平成9年)まで使用されていました。 その後、弘前市が土地を取得、青森県内に次々開館した美術館に呼応するように、1994年(平成6年)の文化拠点施設との構想から26年が経過した2020年(令和4年)にようやく美術館として開館することができました。 この約25年の間、煉瓦倉庫を所有していた吉井酒造と弘前市との交渉条件が合わなかったのですが、青森県立美術館に「あおもり犬」をはじめ多数の作品がある、弘前市出身の美術作家・奈良美智の作品を観た当時の吉井酒造社長・吉井千代子氏の申し出によりこの煉瓦倉庫での奈良美智の個展が三度開かれ、その後、美術館に至るきっかけとなれたようです。 リニューアルでの大きな特徴である、チタン金属板による菱葺き屋根は、光の反射によってシードルゴールド色に輝きます。 |
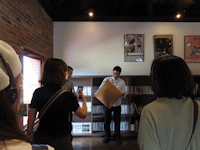 |
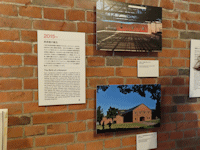 |
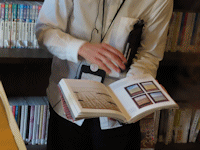 |
| チタン金属板 | 再生した頃 | 色の変化 |
 |
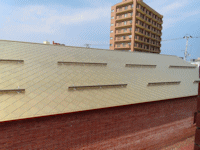 |
 |
| 実際に見ると角度で違って見えます | おー | 模型 |
| これ、実は景観条例に当初引っかかったそうで、その時の反論としては、「色を塗っているのではなく、素材としての色。元はシルバーであり、光によってゴールドに見える。」ということでOKをもらえたそうです。 |
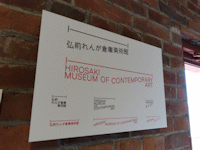 |
||
| ロゴデザイン |
| 窓にはロールスクリーンが設置されていますが、できるだけ当時のふんいきを損ないたくないとのことで、下から上に上げるスクリーンとしたそうです。 メーカーも想定していない使い方ですね。 |
 |
||
| 下にロールスクリーン |
| 耐震補強工事もしたそうで、煉瓦壁にせん孔を開け、鉄筋(というよりはPC鋼でしょう)を伸ばした状態で差し込み、最後に引っ張りを解除して上下で押さえつけているそうです。 レンガ自体は強度のある材料ではないと思うのですが、大丈夫なのかなぁ。 当時の写真と、現在の様子を比べながら説明してくださいます。 |
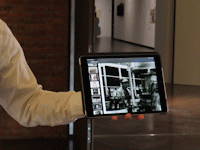 |
 |
|
| 当時の様子 | 天井裏 |
| 屋根裏にあたり、梁裏に、井戸水を貯めるタンクがあります。 ここに貯めた水をパイプでさまざまなところに引いていたそうです。 |
 |
 |
 |
| タンク | パイプが残っています | 今は水貯めていませんよ |
| 1階に降ります。 美術館のエントランス部分の煉瓦積みについては、千葉県から職人さんが来られたそうです。 90度交互にしながらカーブを描く、イギリス積みでもフランス積みでもないこの積み方を、建築家・田根剛は「弘前積み」と名付けたそうです。 |
 |
 |
|
| 弘前積み | すごいなぁ |
| エントランス中の壁には穴がいくつも空いています。 レンガ壁には漆喰が塗られていたそうですが、それを斫った跡だそうです。 |
 |
||
| 穴が開くレンガ |
| 外に出ます。 この美術館は2020年(令和2年)2月末に開館予定でした。 エントランスのレンガ積みは1月末に一旦完成しましたが、職人さんが気に入らないからと積みなおしたそうです。 開館にはギリギリ間に合ったそうですが。 |
 |
||
| きれいです |
| お隣の煉瓦倉庫は、シードル工房兼ショップですが、元々はエントランス部のみが煉瓦で、残りは木造だったそうです。 |
 |
 |
|
| 色が違うところで新旧かな | いいですねー |
| 隣の建物のレンガ積みは、元々は地元の工務店さんが積んでいたそうですが、このまま積むとエントランス部のレンガ積みとの違和感が出ると言うことで、エントランス部分を積んだ千葉の職人さんが「タダでいいので積まさせてほしい。」ということで積まれたようで、100年前の建物と合うような積み方をされたそうです。 というわけで、下から1mくらいまでとそこから上は違いがあります。 |
 |
 |
|
| 違和感がないように | 新旧はわかっちゃいますね |
| 再度中へ。 美術館を観ていきます。 普通、美術館の展示空間は、とりわけ近現代美術を扱う施設では、直線に囲まれた真っ白いニュートラルな壁の「ホワイトキューブ」が理想とされます。 しかし、こちらではコールタールが塗られたダークな壁となっています。 倉庫時代に、防虫・防腐の目的でコールタールが使用されたということからだそうで、床のコンクリートにも炭が混ぜられ、黒っぽいものとしています。 |
 |
 |
|
| ボルトではなくリベットの時代の鉄骨接合部 | 天井もダークな感じで |
 |
 |
|
| コールタールの壁 | 墨を練り込んだコンクリート床 |
| あまりない暗い感じの美術館ですが、作品によってはこれもありですね。 |
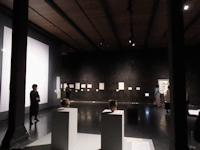 |
||
| シック |
| 作品によっては、展示指示書に光りを求めるものもあるそうです。 で窓からの光りを入れたり。 |
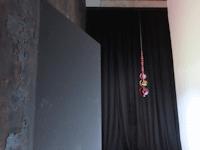 |
||
| "ぶらさがる恋人"ジャン=ミシェル・オトニエル |
| エレベーターで上がりますよ。 |
 |
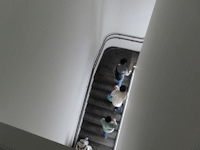 |
|
| ステンレスなエレベーター | 階段 |
| アイアンなものたちもいい感じですね。 |
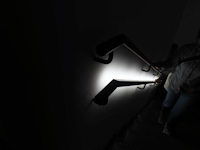 |
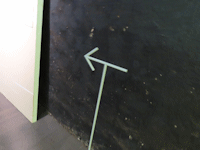 |
|
| 手摺ステキ | 順路表示 |
| 2階から眺めます。 |
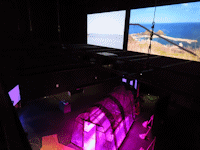 |
 |
|
| 吹き抜けな感じの展示 | 屋根裏 |
| 奈良美智が弘前高校在学中に開店準備にたずさわり、アルバイトをしていたロック喫茶を再現した作品、「JAIL HOUSE 33 1/3」が展示されています。 ロック喫茶はアパート1階のガレージを改造して造られ、その内装やテーブル、椅子、カウンターまで作り、壁には絵を描いたのだといいます。 実店舗は1980年代半ばには既に閉店し、現在は新しいビルが建っているそうです。 |
 |
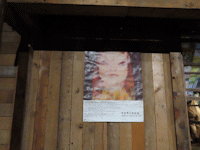 |
 |
| "JAIL HOUSE 33 1/3"奈良美智 | 過去の青森県立美術館での奈良美智展 | いいですねー |
 |
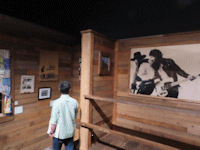 |
|
| ボトルキープたくさん | ブルース・スプリングスティーンのポスター |
| 1階へ。 アップルブランデーを使った作品がありました。 窓に強化合わせガラスを嵌め、その間にニッカウヰスキーのアップルブランデーを入れ、そこを通して景色見るのです。 |
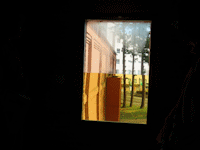 |
||
| "AMBER WINDOW (HIROSAKI)"和田礼治郎 |
| いやぁ。よかったですよ。 |
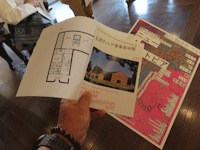 |
||
| 資料いろいろ |
| ということで、見学終了。 少し自由時間です。 ショップでちょっと買い物するかな。 シードルの飲み比べができるようですが、そこまでの時間はないな。 |
 |
||
| シードルのタンク |
| 缶買ってバスで飲もう。 あと、美術館の所蔵作品ではなく、そのものについての図録があったので購入。 |
 |
 |
|
| トイレもいい感じ | この手の手洗いはよくあるかな |
| 改めて外観を眺めます。 |
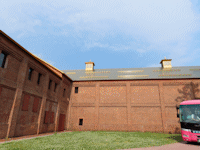 |
 |
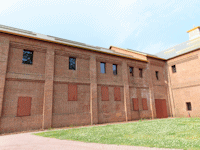 |
| チタンの屋根 | 塔屋 | いいですねー |
| バスに乗り込み、シードルいただきました。 |
 |
||
| 白神ワイナリーGARUTSU LAUNCH UP HARDCIDER LEMON DROP |
| -15:50- では移動します。 |
 |
||
| ありがとうございますー |
| 県道260号を戻ります。 ところで、雪国は軒樋がないそうです。 雪の重みで潰れてしまうからだそうです。 そうなんだ。毎年宮城に行っているけど気づかなかったなぁ。 秋にまた行くのでちゃんと見ておこう。 |
 |
||
| ほんとだ!軒樋ない! |
| そしてR7・弘前バイパスへ。 -16:15- 東北道・大鰐弘前ICで再び高速に。 |
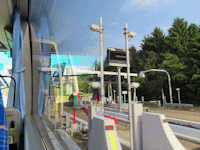 |
||
| 高速乗ります |
| -16:30- 岩手県に入ります。 |
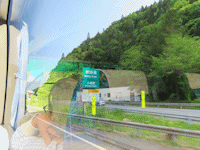 |
||
| さよなら青森県 |
| 途中、道路工事で反対車線を走ります。 |
 |
||
| 逆走じゃないよ |
| -17:05- 安代JCTを通過します。 |
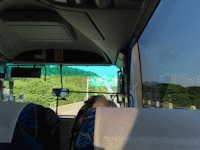 |
||
| 八戸道とのJCT |
| 山が見えてきましたね。 |
 |
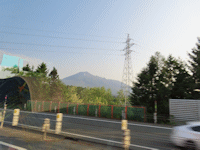 |
|
| 八幡平かなぁ | 岩手山かなぁ |
| -17:25- 東北道・岩手山SAで休憩です。 |
 |
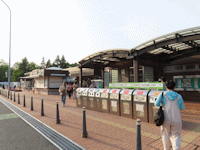 |
 |
| SA入ります | 岩手山SA | 岩手山です |
| それではあとひき行きましょうー。 |
 |
||
| また工事で反対車線を走る |
| 日が暮れてきましたね。 |
 |
||
| 関西よりは少し日の入りが早い |
| -18:10- 東北道・紫波ICで降ります。 |
 |
||
| 紫波です |
| 県道162号から県道46号を東へ。 そして、市道を走ります。 |
 |
||
| きれいな街並みに入る |
| -18:20- バスを降りて、本日のお宿「オガールイン」に到着しました。 |
 |
 |
 |
| 紫波町役場 | オガール | オガールインへ |
| 「オガール」は、公民連携による公有地の活用を行った取り組みで生まれた街です。 「成長」を意味する紫波の方言「おがる」と「駅」を意味するフランス語「Gare」(ガール)を組み合わせた造語です。 JR紫波中央駅前を「紫波の未来を創造する出発駅」とする決意と、このエリアを出発点として紫波が持続的に成長していく願いを込めたそうです。 紫波町の人口は約3万人ですが、高速のインターチェンジや3つのJRの駅があるなど、なんともポテンシャルの高い町です。 図書館を見学したかったのですが、土日祝は18時まで、朝も10時からなので無理ですね。残念。 |
 |
 |
|
| 薪ストーブ | 全日本のバレーボールチームも来ています |
| チェックイン手続きをしていると、スポーツ少年たちの団体さんが。 そして、とりあえず部屋へ。 部屋割りでは東京からご参加の方との2人部屋です。 よろしくお願いしますー。 では、すぐに夕食へ。 -18:00- 夕食はオガールにある、居酒屋「二代目真魚板」さんです。 |
 |
||
| 二代目真魚板さん |
| ここで建築士会の女性会員さんが5名が前田由利さんと交流するので参加されるとのこと。 そのうちのお一方が、バイクで岩手県内を走り回り、個人的に芝棟調査をされているそうです。 2万km走り倒して調査したのだとか。すごいなぁ。 |
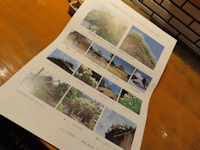 |
||
| おー |
| 飲み物、何にしますかね。 |
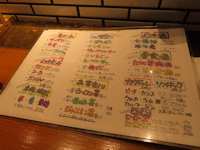 |
||
| いろいろある |
| 飲み物が来るのにあわせて食事も来ますよ。 |
 |
 |
|
| お刺身とサラダ | 生ビール |
| それでは、前田由利さんの御発生で開始ですー。 |
 |
 |
|
| ご挨拶 | かんぱーい |
| カウンター席でいただきました。 |
 |
 |
|
| いろいろと | 炙り〆さば |
| 日本酒いきますか。 |
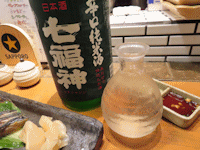 |
 |
|
| 岩手県雫石町・菊の司酒造 辛口純米酒 七福神 |
岩手県釜石市・浜千鳥 浜千鳥 純米酒 |
| 紫波町のお酒はなかったですな。 七福神のほうが好みでした。 お店の方に、オガールができるまではここは何だったのかを聞いてみたのですが、「雪捨て場」というお返事。 町有の空き地だったようですね。 |
 |
 |
 |
| 鶏 | 磯辺揚げ | レバー |
| 釜飯の準備が始まりました。 |
 |
||
| おいしくなーれ |
| そして、コースが食べ終わり、ちょっと追加。 |
 |
 |
 |
| 魚のフライ | 鶏 | ハイボールにシフト |
 |
 |
|
| 干物 | 最後はアイス |
| 楽しくいただき、終了となりました。 もうちょっと飲みますかー?としても飲む場所がないので、部屋に戻り、大浴場に行きますかということになり解散。 大浴場に行くと、ちょうどチェックインの時にいっしょだった子供たちと鉢合わせます。 オガールには日本初のバレーボール専用コート「オガールアリーナ」があります。 オリンピックでも正式採用されているフランスGerflor社製タラフレックスを床材に使用しているそうで、全日本チームが合宿で使用したりしています。 このバレーボール専用コートもあってか、人口約3万人の町に、今や年間100万人が訪れるそうです。 ただ、この公民連携のまちづくりが進むまでは、10年ほど塩漬けになっていた土地だったそうです。 だから、二代目真魚板の方が「雪捨て場」と言っていたのですね。 で、子供たちに「バレーボール?」と聞くと、バスケットとのこと。 多目的スポーツ施設のサン・ビレッジ紫波か、ちょっと離れますが岩手県の総合体育館があるので、そこで合宿練習かな。 風呂上り、明日は朝6時半の朝食開始時間に行きましょうかということで、早目に寝ます。 本日の東北走行距離 233km 明日は芝棟三昧となりますよ。 |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.