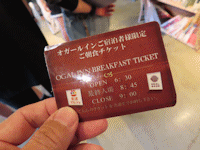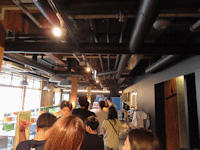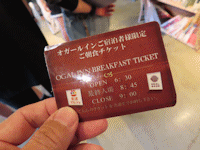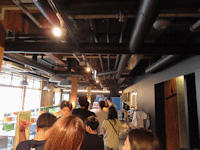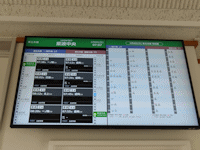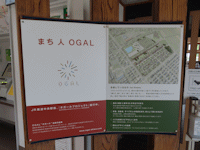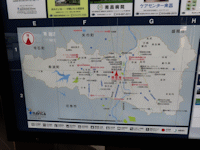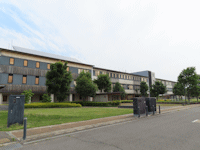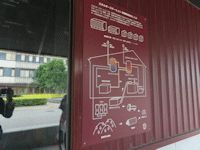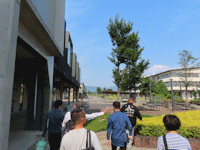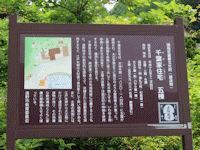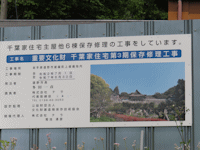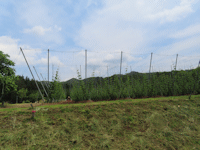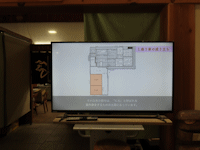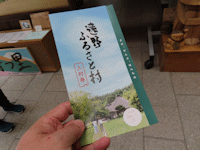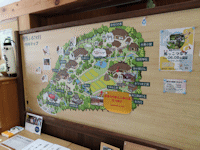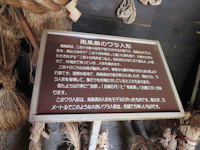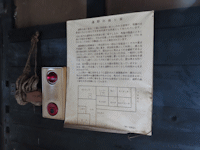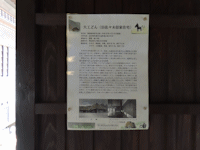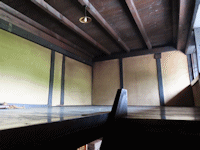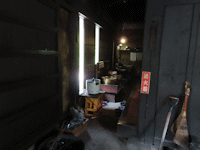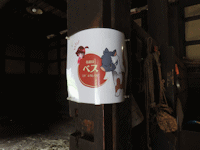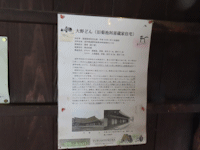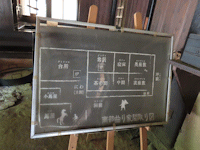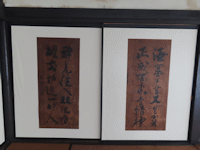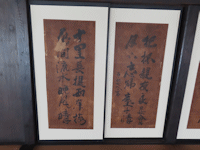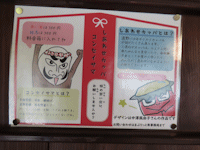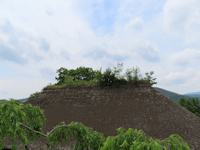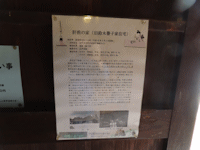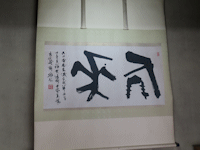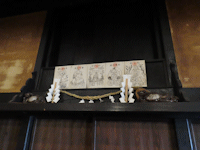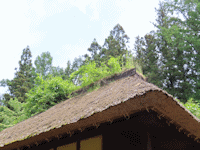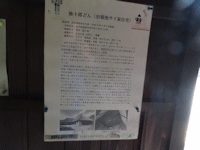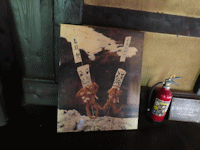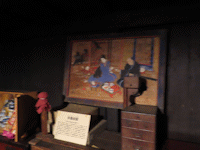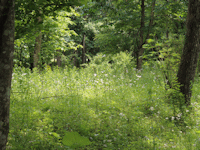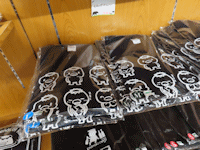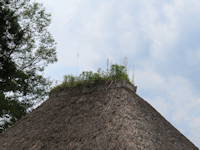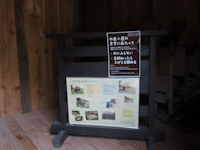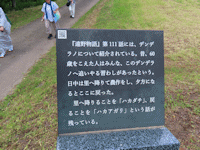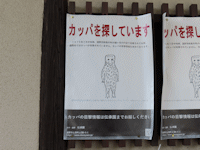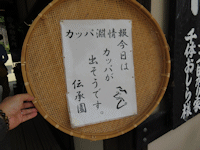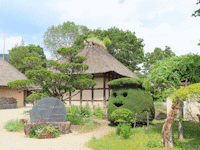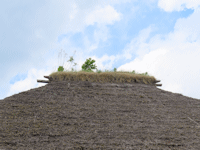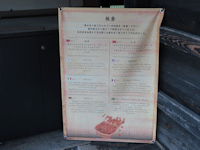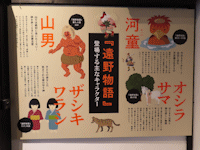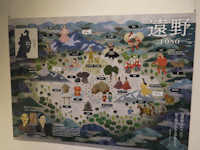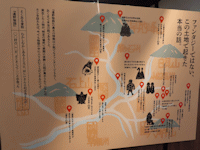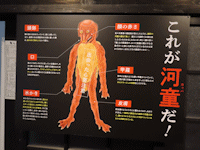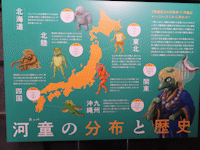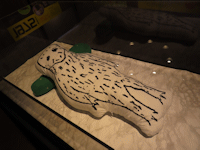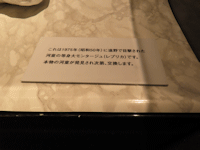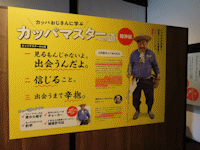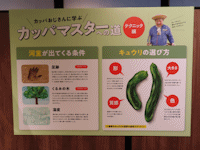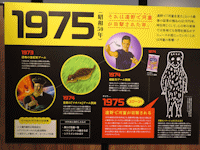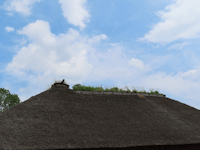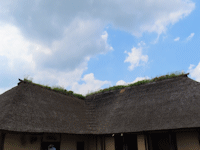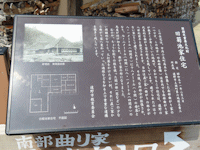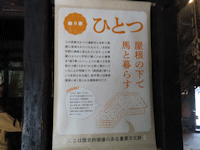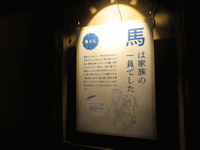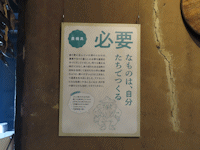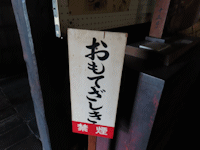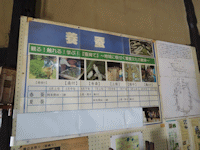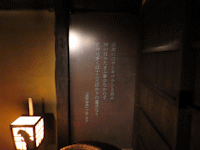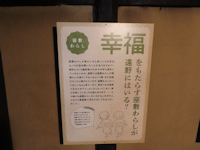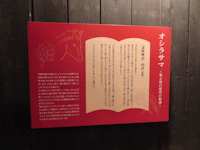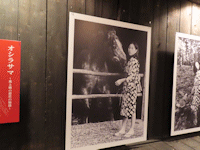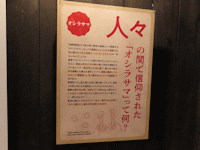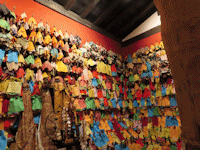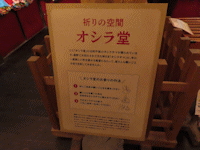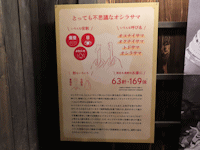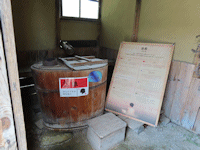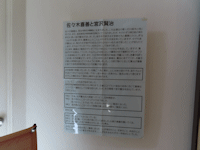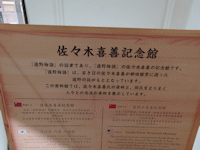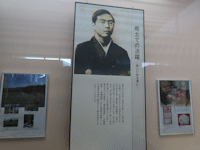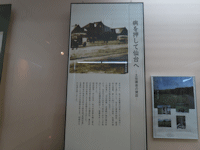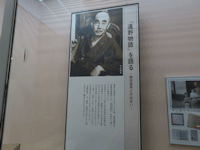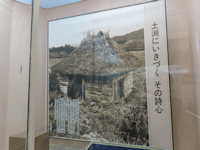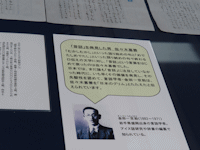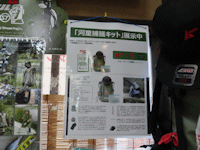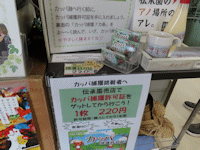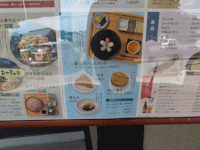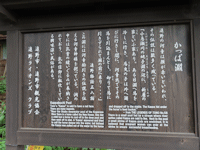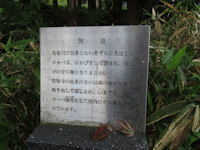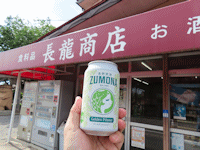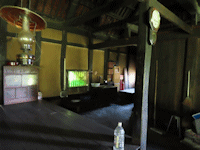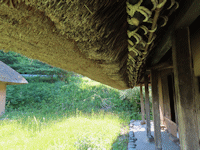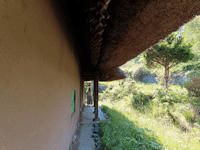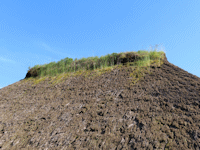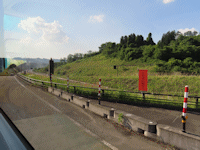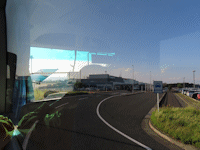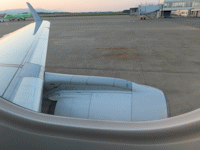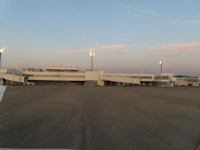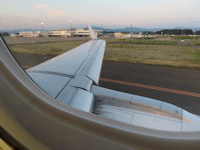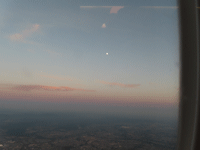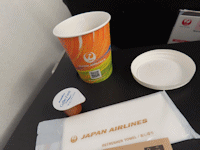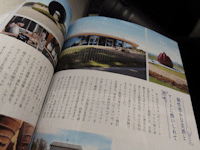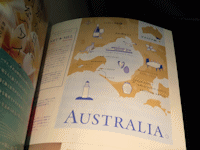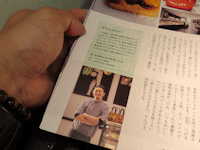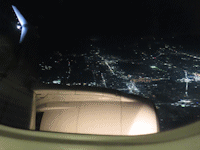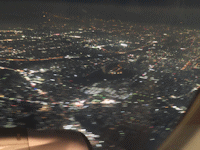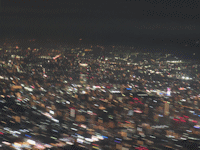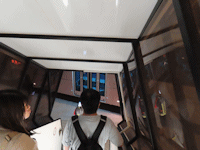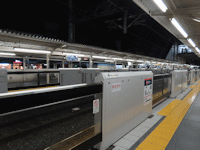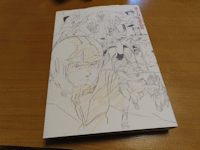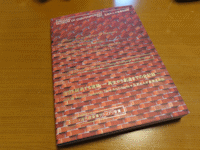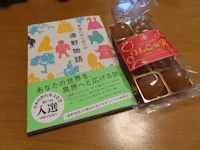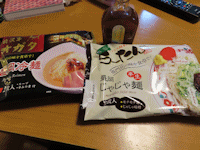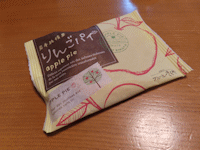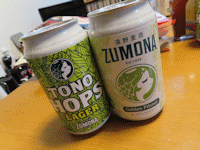RockzGoodsRoom > Outing > Outing2025 >
RockzGoodsRoom > Goods >
青森・岩手(草屋根の遠足・青森〜岩手ツアー) (2025/06/07〜08)
←1日目はこちら
昨日は青森から岩手に移動し、公民連携でできた街、オガールに泊まりました。
今日も1日盛りだくさん。楽しんでいきましょう。
6月8日(第2日)
-06:00-
目覚めます。
ささっと出発準備をして、荷物はそのまま、とりあえず朝食会場に行きましょう。
-06:25-
昨日、チェックインの時には、団体さんもいるので、朝食会場は混みますと言われていましたが、まだ最初の一巡目では十分座れるくらいしか並んでいませんね。 |
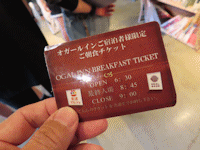 |
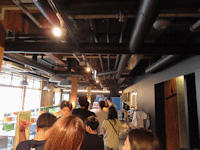 |
|
| 朝食チケット |
まだましな列 |
|
-06:30-
朝食会場オープンです。
バイキング形式ですよ。 |
 |
|
|
| いただきますー |
|
|
美味しくいただきました。
8時にオガールを管理している紫波町情報交流館の方が出勤してこられて、少しご案内をしていただけるそうです。
それまでちょっと散歩しましょうかと、同室の方とうろうろすることにしました。
まずは、JR紫波中央駅に行ってみましょう。
オガールベースをてくてく東へ。
端にファミリーマートがありました。 |
 |
 |
|
| オガールベース |
ファミマ |
|
| 幹線の市道のところには、ポケモンマンホールがありました。 |
道を渡り、駅のほうへ。
なんだか、すごい列車の通過音がします。 |
 |
 |
|
| 駅前ロータリー |
JR紫波中央駅 |
|
駅にやってきました。
駅の開業は1998年(平成10年)ですが、駅舎は林野庁の補助事業により2001年(平成13年)に町産の木材が使われた木造平屋建てで完成しました。
正式には「紫波中央駅待合施設」と称する町の施設だそうですよ。
紫波町が東経140度57分、北緯39度28分に位置することから、使われた部材は140、57、39、28にちなんだ寸法が多用されているらしいです。
だいたい、1時間に2本列車が来ますね。
朝は少し多いけど。 |
朝からお掃除されている方もいました。
ボランティアの方もいるようですが、日中の管理は業務委託により管理人が置かれているようです。 |
 |
|
|
| きれいにされている |
|
|
| あー、在来線に並行してすぐ隣に東北新幹線が通っているのですね。 |
 |
|
|
| すげぇ音は新幹線 |
|
|
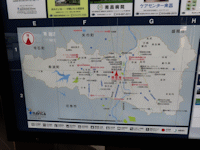 |
|
|
| 盛岡市にも接しているんだ |
|
|
 |
 |
|
| オガールプラザ |
案内図 |
|
 |
 |
|
| 緑のバッファ |
電柱がないな |
|
てくてく幹線を歩いていると気づいたのですが、幹線沿いに住宅の出入りがないのですね。
一旦、住宅街に入ってからの道でアクセスするようになっています。
もちろん、街区から幹線道路に抜ける人の通り道はいくつか設けられています。 |
 |
 |
|
| こちら側には出入りない |
車は通れない通り道 |
|
遠くに岩手県立紫波総合高等学校が見えますね。
街区内に入ってみます。
新たな住宅街ですね。
景観配慮のためか、電線がないですね。各戸の塀もほとんどなく開放的。 |
 |
|
|
| 道路も広い |
|
|
西へ進んでいくと公園がありました。
公園の向こうは畑が広がっています。 |
 |
 |
|
| 広々 |
芝生の向こうは畑 |
|
南下していきましょう。
ふと気づいたのですが、プロパンガスが多いと言うイメージなのですが、都市ガス通っているのですかね。
メーター類が設置されています。 |
 |
|
|
| 灯油タンクは必須 |
|
|
神社がありますね。
これは昔からあったのでしょう。 |
 |
|
|
| 薬師神社 |
|
|
保育所があったり、エネルギーステーションがあったり。
エネルギーステーションってなんだろう。 |
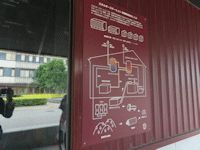 |
|
|
| バイオマスかな |
|
|
オガールベースに戻ってきました。
皆さんも思い思いに過ごされていた模様。 |
 |
 |
 |
| オガールの中央の道 |
昨夜の「二代目真魚板」さん |
泊まったオガールインのあるオガールベース |
-08:00-
仕事でこちらに来られていた、草屋根の会法人会員の、大林環境技術研究所の大林社長のツテで、紫波町情報交流館の高橋事務局長からご案内いただけることになりました。 |
 |
|
|
| よろしくお願いいしますー |
|
|
オガールプロジェクトは、10.7haの町有地を整備したものです。
元々は1998年(平成10年)に再開発のために紫波町が取得したものですが、不景気による税収減などの理由により再開発事業は頓挫し放置されていました。
その後、公共施設の集約なども含め、2009年(平成21年)に公民連携事業として再スタートしました。
最初に完成したのは2012年(平成24年)のオガールプラザです。こちらには情報交流館や図書館が入っています。
木造ですが耐火のためにコンクリートの壁が間に入っていて、3エリアに分かれているそうです。
産直施設も入っています。
紫波町は、産直市越の多い町だそうで、元々町内には10箇所あったそうですが、今は8箇所に集約されてきているとのことでした。 |
 |
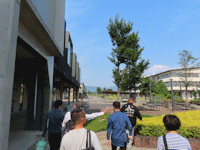 |
|
| よく管理されています |
説明を聞きながら移動 |
|
2014年(平成26年)にオガールベースができました。
こちらには、日本初のバレーボール専用コートである「オガールアリーナ」があります。
野球やサッカーは日本中どこにでも施設があり、誘致しても目新しさやうまみがないようで、スキマ産業ではないですが、誰も目をつけていないところに着目したと言うところですね。
これを「ピンホールマーケティング」と言うそうです。隙間以上に針の孔を狙うさらにハイレベルなマーケティングですね。
2015年(平成27年)に紫波町役場庁舎ができましたあ。
町産のカラマツを使った、国内最大級の木造役場となっています。
一番新しいのは2017年(平成29年)にできた、オガール保育所です。
草屋根の会の法人会員である、大林環境技術研究所の大林さんによると、オガールプロジェクトのランドスケープは、星野リゾートの「星のや」のランドスケープも多く手掛けた、オンサイト計画設計事務所の長谷川浩己氏(武蔵野美術大学教授)が手掛けたそうです。
最近では、盛岡動物園再生事業に出資するオガールと共に、オンサイト計画設計事務所もランドスケープの設計に携わっているそうです。
調べると、オンサイト計画設計事務所が手掛けたランドスケープは、以前行った新山口駅北口駅前広場「0番線」、あべのハルカス屋上庭園なんかも手掛けていたのですね。
高橋事務局長によると、緑の維持が大変だということです。
10年たってもこれだけきれいに保たれているのは高橋事務局長はじめ、勤務時間前にボランティアとしてゴミ拾いや草抜きをされているからということです。
そうなんですよね。施設の維持管理ってお金をかければ当然維持できるのですが、そこが続かないので困ったものなんですよね。 |
 |
|
|
| ハスクバーナの草刈りロボットも活躍中 |
|
|
西側の公園まで来ました。
この公園は「クローバー公園」と呼ばれているそうです。クローバーが大量増殖しているからとのこと。
その向こうは畑ですね。今は、麦だそうです。 |
 |
|
|
| 通称クローバー公園 |
|
|
岩手県のフットボールセンターがあります。
これは町が県に働きかけて誘致し、2011年(平成23年)に完成しました。
これにより、バレーボールだけでなく、サッカー関係の人も来るようになっているのだとか。
戻っていきます。
エネルギーステーションは2014年(平成26年)に完成し、役場とオガールセンター、保育所、そしてオガールタウンの57戸に給湯、暖房・冷房を有償供給しています。
木質バイオマスボイラー等を活用し熱供給をしています。
紫波グリーンエネルギーという会社がインフラ整備と熱供給事業を行っているという図式のようです。
木質バイオマスということで、紫波町は林業が盛んなのか聞いたのですが、そうではないとのこと。
調べると、使われている木材は、町内の松枯れ材、未利用材、土木支障木等だそうです。
松枯れ材や未利用材の収集には、町が地域振興券の交付をあわせた市民参加型の仕組みを導入し、搬入者には現金+地域振興券が支払われるそうです。
その背景には、紫波町が松枯れの激甚被害地であり、伐採後は林内薬剤処理が主流で景観や災害防止の点で課題となっていたことにあるようです。
農林公社がこの仕組みを活用し、町民に呼びかけ「間伐材運び隊」を組織、農林家・非農林家を問わず様々な住民が参加できる体制をつくり推進しているとのことです。
電気は東北電力を引いているのでしょうけど、給湯、冷暖房があるなら、プロパンガスは必要ないので、住宅街にはガスが確認できなかったのかも。
そして、メーター類が同じように配置されていたのは、使用量を検針し、売電ならぬ「売熱」するためですね。
産業としては、醸造業が特徴だそうで、町内に4つの蔵があります。
紫波町は日本三大杜氏のひとつである南部杜氏の発祥地とされています。
そこまで聞いて思い出しましたが、日本酒キャピタルの田中文吾さん(秋田・大納川のビッグボス)の3号案件で2022年から手掛ける「紫波酒造店」がありましたね。
あー、お伺いするには時間がないなぁ。同じ町内でも距離があるし。
オガール広場では、フリーマーケットでもあるのか準備が進んでいました。
この広場も、当初の計画では駐車場になるはずだったそうですが、町の人が憩える場所ということで広場としたそうです。
というわけで、高橋事務局長ありがとうございましたー。
一旦部屋に戻り、荷物を持ってチェックアウト。
-09:00-
では、出発です。
新栄観光バスさん、今日もよろしくお願いします。
町道から県道25号に入り、北上川を渡ります。
河口は宮城県石巻市なので延長は長いですね。 |
 |
 |
|
| こんなところにも北上川 |
田んぼは水が満々 |
|
R396を南下します。
今日は、予定にはなかった芝棟を一か所追加したいと言うことで、当初の予定から少しずつ時間を削って調整することになりました。
-09:55-
旧千葉家住宅に寄ります。
こちらは重要文化財で、南部曲り家千葉家と言われるものです。 |
 |
 |
 |
| 旧千葉家住宅 |
屋根は葺き替えられてキレイ |
芝棟も復活 |
 |
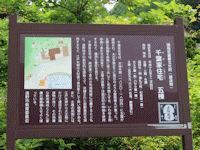 |
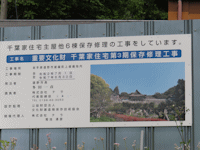 |
| 令和9年3月まで続くらしい |
5棟あるんだ |
第3期工事は今月末まで |
江戸時代の南部地方特有の住居と馬屋を平面L字形に連結した農家建築「曲り家」を代表する建物として知られています。
旧千葉家住宅は日本最大級の曲り家です。
江戸時代後期の天保年間(1830〜1844年)、4代目当主の千葉喜右衛門によって主屋が建てられたそうなので、築200年にはなっている建物ですね。
ここに25人と20頭の馬が住んでいたらしく、大豪邸だったようです。
2016年(平成28年)から保存修理が始まり、現在も続いています。
内部は見学できませんが、現在は主屋の茅葺の葺き替えが終わったようで、屋根が見える程度とのことで立ち寄りましたが、なんとか観られてよかったです。
ちなみに、旧千葉家住宅は日本十大民家のひとつになっているそうですが、残りの9件はどう調べても不明なままです。 |
 |
|
|
| 旧千葉家住宅でした |
|
|
では移動します。
R398を走ります。
そしてR283を東へ。
お昼ご飯に予定している、道の駅「遠野風の丘」の前を通過しますが、うわぁ。車の数がすごいなぁ。
R340に入り、県道160号を北に走ります。 |
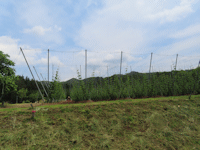 |
|
|
| ホップ畑だ |
|
|
 |
 |
 |
| やってきました |
遠野ふるさと村 |
ビジターセンター風樹舎です |
当初の予定では、ここを見学してから先ほど通った道の駅で昼食。
またこちらまで戻ってきて近くの「伝承園」となっていました。
道の駅、お昼前でもすごい混みようだったのと、道の駅まで行って帰っての時間も短縮できることから、ふるさと村でお昼も済ませれば?という提案をしたところ、そうしましょうということになりました。
というわけで、こちらで見学と昼食を済ませることに。
「遠野ふるさと村」は、8.8haの敷地に、遠野郷に残された、江戸時代から大正時代にかけて建てられた貴重な南部曲り家7棟を移築して遠野の山里を再現しています。
いろいろと体験メニューもあるようですが、今日はそこまではできないですね。 |
| いろいろと時代劇などロケにも使われているようですね。 |
 |
|
|
| 伊武雅刀さんのサインだ! |
|
|
ビジターセンターで受付を済ませ、各自散策します。
パンフレットの地図を見ながら進みます。 |
 |
 |
|
| 川を渡ります |
清流だなぁ |
|
 |
|
|
| 自然史博物館です |
|
|
靴脱いで上がります。
動物や昆虫の標本がいっぱいでしたよ。 |
 |
 |
|
| 熊だ |
虫たち |
|
|
 |
 |
|
小動物や鳥 |
テン |
 |
|
|
| 気持ちいいですね |
|
|
| 門前(かどまえ)を通り、タイムスリップ!だそうです。 |
 |
|
|
| 門をくぐる |
|
|
「大工どん」に来ました。
花巻市大迫町から移築された、明治中期築の旧佐々木四郎家です。 |
 |
|
|
| 「大工どん」です |
|
|
遠野の曲り家とは少し違うようです。
2007年、アニメ映画「河童のクウと夏休み」にこの家が登場したそうですよ。
中では、何やら体験メニューをしていました。 |
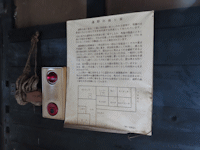 |
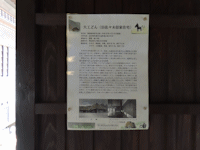 |
|
| 遠野の曲り家 |
大工どんの解説 |
|
 |
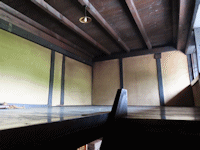 |
|
広いね
「守りっ人」(まぶりっと) |
中二階があります |
|
| 体験イベントをしているので、実際に台所も使われていたり。 |
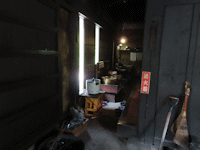 |
|
|
| まぁ薪ではないですが |
|
|
「川前別家」に来ました。
川の前に立っていた川前宅のため、川前別家と呼んでいるそうです。
遠野市土淵町から移築、江戸末期(安政年間)築の旧川前シメ家です。 |
 |
|
|
| 「川前別家」 |
|
|
| QRコードで資料が見られるようで、多言語に対応しているようでした。 |
 |
 |
 |
| 日本語で書いている程度の内容と思いますが |
遠野のしし踊り |
土間にかまどがあります |
 |
 |
|
| 襖外すと広いですね |
囲炉裏 |
|
|
 |
 |
|
梁の上には切り欠きがありますね |
縁側 |
 |
 |
|
| 棟の端 |
水 |
|
屋号か何かかなぁと思っていたのですが、前田由利さんによると、火災から建物を守る火伏せのまじないだそうです。
帰宅後調べると、庶民には許されなかった懸魚(げぎょ)の代わりに水と言う文字を描くことで火伏せのまじないとしたようで、江戸時代末期に始まり明治の頃に定着したそうです。
懸魚とは神社やお寺などの破風板部分に彫刻を施し取り付けられた妻飾りのことで、元々は中国で水と関わりの深い魚を屋根に懸けることによって、火に弱い木造の建物を火災から守るために火伏せのまじないとして取り付けた事によるそうです。
次行きましょう。
ここで気づいたのですが、それぞれの建物に付属する、屋外トイレ(観光用に設置)は、どれも芝棟になっていますね。 |
「大野どん」に来ました。
附馬牛町大野集落の上層農家として建てられました。奥座敷の襖に書かれたこの地方の名もなき書家の漢詩があります。
遠野町附馬牛町から移築、明治初期築の旧菊池利喜蔵家です。 |
 |
 |
|
| 「大野どん」 |
違和感のないトイレ |
|
 |
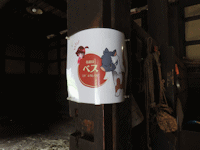 |
|
| ポニー |
ベスだそうです |
|
シェットランドポニーというそうです。
ベスは1995年(平成7年)生まれの牝馬だそうです。 |
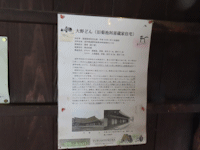 |
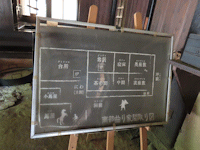 |
|
| 解説 |
間取り |
|
馬屋に釜がありますが、これは「馬釜」と呼ばれています。
寒さの厳しい冬に、馬屋を暖めたり、温かい食事を馬に与えたそうで、やさしさの釜ですね。
ただ、豆腐や味噌をつくる豆を煮たり、蚕の繭をほぐすために湯につけたりといった作業にも使い、煙を出すことで茅葺き屋根虫がつかないよう燻したりもしたそうです。 |
 |
|
|
| 馬釜 |
|
|
2007年、NHKの朝ドラ「どんど晴れ」遠野篇で石川宅に使われました。
上がらせらいます。 |
| 襖に書かれたこの地方の名もなき書家の漢詩があります。 |
 |
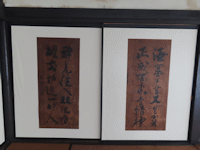 |
|
| 読めないな |
misenさんなら読めるかな |
|
|
 |
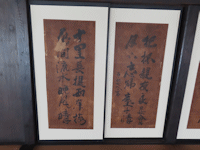 |
|
漢詩というのはわかる |
むー |
| しあわせカッパ、コンセイサマという願掛けがあるようですね。 |
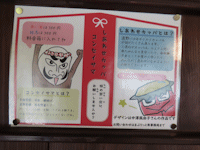 |
|
|
| コンセイサマは金精様=男性を祀る性紳 |
|
|
 |
 |
|
| 囲炉裏 |
馬釜 |
|
 |
|
|
白雪というらしい
26歳 |
|
|
| 馬の寿命は20〜30歳と言われているので、もう結構なお年なのですね。 |
 |
|
|
| 広場を横切っていく |
|
|
「こびるの家」に来ました。
「こびる(小昼)」とは「おやつ」のことだそうです。
遠野市赤川集落の総本家でした。このような直家(すごや)は苗字帯刀を許された人の家で、別棟に納屋、土蔵、廐などがあったそうです。
遠野市上郷町から移築、1762年(宝暦12)築の今は体験教室も行なっている休憩所です。 |
中は見られませんでした。
「肝煎りの家」に来ました。
肝煎りは、庄屋のことです。ふるさと村では一番大きな曲り家となっています。
乗込小屋が付属しています。 |
 |
 |
 |
| 乗込小屋は納屋のことかな |
芝棟 |
門のようになっている |
| 「肝煎りの家」は遠野市綾織町(砂子沢)から移築、江戸末期築の旧鈴木誉子家です。 |
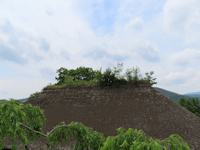 |
 |
 |
| 肝煎りの家の芝棟 |
結構木が生えているなぁ |
馬屋 先ほどの白雪はここが寝床 |
| 縁側には式台と呼ばれるお城や代官所などから、 自分より身分の高い人が来たとき挨拶用件を受ける場所があります。庄屋として格式の高い家です。 |
 |
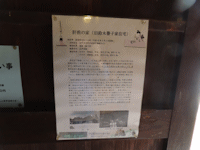 |
|
| 式台 |
解説 |
|
上がらせてもらいます。
さすが、肝煎りの家、広いですね。 |
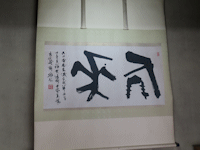 |
|
|
| 最近(平成8年)の書です |
|
|
 |
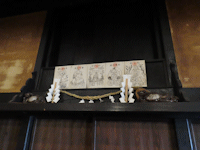 |
|
| 囲炉裏でかいね |
色々な神を信仰 |
|
遠野にも、ここを含めて7つしか水車小屋は残っていないそうです。
郷倉があります。
村ごとに設けた、収蔵用の倉だそうです。年貢米などを一時保管する倉だそうです。 |
 |
|
|
| 郷倉 |
|
|
「弥十郎どん」に来ました。
外からの人に目がふれる所は天井を高くし、居住スペースは天井を低くした、典型的な上層農家の造りをしています。 |
 |
 |
|
| 屋根が苔むしてきている |
弥十郎どん |
|
2階を隠し部屋として造り、仕切りの板壁など武家屋敷以上に防備した造りとなっています。
遠野市宮守町から移築、1812年(文化9年)築の旧菊池サイ家です。 |
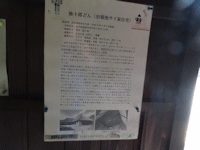 |
 |
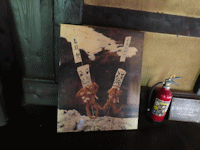 |
| 解説 |
野のしし踊り
南部鶴の家紋だ |
雨風祭の似ているけど旧暦2月の春風祭 |
 |
 |
|
| 階段状の家具 |
中二階 |
|
 |
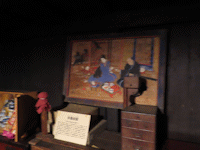 |
|
| 一部天井が中二階だな |
供養絵額 |
|
 |
 |
 |
| 広いね |
「むがす、あったづもな」
昔々あるところに・・・ |
権現様 山伏神楽に登場 |
 |
|
|
| 農機具小屋かな |
|
|
「バッタリ」というのがあります。
三角屋根の小屋で、かつては水の力を利用して精米や製粉を行っていたそうです。 |
 |
 |
 |
| バッタリのある風景 |
バッタリ |
ちょっと痛んでいますね |
 |
 |
|
| 田んぼ |
スミレが咲いている |
|
「水乃口」って染工房として活用されている曲り家がありますが、こちらは茅葺屋根の葺き替え工事をしているため見学はおろか、近づきもできませんでした。
鯉の池で、鯉に餌をあげられますね。 |
 |
 |
|
| よくあるエサ |
《クリックで動画再生》
すごいことになる |
|
今日は、「馬っこつなぎ」というイベントをしているようです。
馬っこつなぎは北上山地周辺の農村に伝わる、田の神様をお迎えし、自然の恵みに感謝し豊作祈願を行う伝承行事です。
田の神様がお供えしたわら馬に乗り、田んぼの植え具合を見まわると言われています。
わら馬づくりを終えた一行が、田の神様にお供えに行っていました。
なぜか、草屋根の会の方も参加されていたり(笑) |
 |
|
|
| 守りっ人に連れられお供えに |
|
|
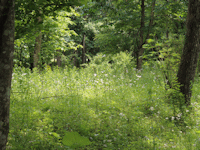 |
|
|
| 木霊出てきそう |
|
|
 |
|
|
| タイムスリップから戻る |
|
|
ビジターセンターに戻ってきました。
お昼食べるかな。
食事処「ばあば」でいただきます。
ひっつみ定食をいただきますよ。 |
 |
|
|
| 待ちます |
|
|
 |
|
|
| ひっつみ定食 |
|
|
美味しいですねー。
そうこうしていると、皆さんも食べに来られました。
食後は、ショップでお土産買いますか。
カッパグッズ欲しいんですけどね。以前、遠野に来た時と品揃え変わっていないので、追加購入はないかな。 |
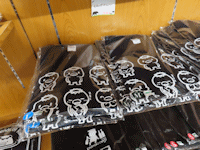 |
 |
|
| このTシャツ持っている |
ふるさと村の模型 |
|
| なんだかレアなものもありましたが、買うのは見送りました。 |
 |
 |
|
| ペヤングの焼きそばじゃないやつ |
かーさんケットにメン子ちゃんミニゼリー |
|
-12:30-
では移動します。
県道160号を戻ります。
そしてR340を東へ。
そして市道に入っていきます。
-12:50-
「山口の水車小屋」にやってきました。
土淵町山口集落にある、今でも現役で動いている茅葺屋根の水車小屋です。 |
 |
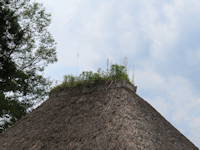 |
 |
| 水車小屋 |
芝棟 |
《クリックで動画再生》
元気に稼働中 |
前田由利さんは、ここに来るのは三度目だそうです。
いつごろ建てられたのかは不明ですが、かつてはこの周辺にも水車小屋は複数あったそうですが、現在でも使われているものはここただただひと棟だけだそうです。
しかし、この水車も長らく使われていなかったのが、2016年(平成28年)に修理して使える水車となったそうです。 |
 |
 |
 |
| 水車 |
《クリックで動画再生》
結構なスピードが出ています |
いいねー |
 |
 |
 |
| こじんまりしています |
よくぞ残っていましたね |
芝棟かわいい |
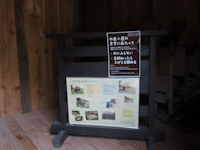 |
 |
|
| 入らない 見たら閉める |
水車の機構 |
|
|
 |
 |
|
穀物突いたりするんですね |
《クリックで動画再生》
水車の様子 |
| いやぁ。ほぼ新築状態になっていますが、修復されてよかったですね。 |
 |
 |
|
| 軒先 きれい |
見どころはいろいろあるみたい |
|
 |
|
|
| ローカル車両に阻まれる |
|
|
出発してすぐ、前田由利さんがスマホで「山口デンデラ野」というのを見つけました。
運転手さんに行けないか聞いてみたところ、「行けますよ」と寄っていただけることになりました。
R340を戻って行っていたので、そこから市道に入って元の道に戻ります。
さらに細い市道に入っていきます。
-13:15-
バスを降りて少しだけ歩き、「山口デンデラ野」に。 |
 |
 |
 |
| 姥捨てされた人々の家ですね |
ここで生活 |
かわいい芝棟 |
遠野物語の姥捨て伝説の地にある原野です。
遠野物語111話「山口、飯豊、附馬牛の字荒川東禅寺および火渡、青笹の字中沢ならびに土淵村の字土淵に、ともにダンノハナという地名あり。その傍らにこれと相対して必ず蓮台野(デンデラノ)という地あり。昔は六十を超えたる老人はすべてこの蓮台野へ追いやる習わいがあり。老人はいたづらに死んでしまうこともなるぬゆえに、日中は里へ下り農作して口を糊したり。そのために今日も山口土淵周辺にては朝に野に出ることをハカダチといい、夕方野より帰ることをハカアガリという。」
姥捨てと言っても老人もただただ死ぬわけにはいかず、日中は里に下りて農作業に従事して生活していたそうです。
そのため、山口、土淵の辺りでは、朝に田畑へ働きにでることをハカダチと呼び、夕方に帰っていくことをハカアガリと呼ぶと云われていました。
その際に使った住居の復元、アガリの家がここにあります。
ハカは、「墓」ではなく、近畿、九州、北陸、関東、東北、北海道などで広く使われている方言で「仕事」を意味するそうです。
古くは米などの収穫予想量を言ったもので漢字では「捗、計、量」が当てられます。
「ハカが行く」とは、「仕事が順調に進捗する」という意味になります。
この意味の「ハカ」から、「仕事がはかどる」や、
物の量や大きさを数値化する「計る、測る」、
計画を立てるという意味の「図る」なども生まれたようです。 |
 |
|
|
| デンデラ野でした |
|
|
近くに、ダンノハナという場所もあります。山口集落を挟んでデンデラ野と向かい合う東側の丘にあります。
生の空間の集落、死の空間のダンノハナ、その中間がデンデラ野として解釈されています。
ダンノハナは「壇の塙(だんのはなわ)」から来ているという説が有力視されています。「壇」は日本語でも「お墓」の意味で「塙」は「土が高い」と書くため、繋げると「お墓の丘」ということになります。
実際、共同墓地があり、そこには遠野地方の土淵村出身の民話蒐集家であり小説家でもあった佐々木喜善の墓もあります。
「遠野物語」は、この佐々木善喜が語った遠野地方に伝わる伝承を民俗学者・柳田国男が筆記・編纂する形で出版されたものです。 |
 |
|
|
| 日本の風景だなぁ |
|
|
では行きますか。
市道からR340に戻ります。
そして市道へ。
-13:35-
「伝承園」にやってきました。 |
 |
|
|
| 新奥の細道なんだ |
|
|
実はこちらには以前来たことがあったのですが、かっぱ捕獲優先でしたので、昼食利用だけで施設は観ていなかったのですよね。
どうやら昨年春にリニューアルしたようです。 |
「乗込長屋」は1850年(嘉永3年)頃に建てられた農家・旧菊池家住宅の納屋を移築したもので、物置や作業場として使われた建物です。かつては、玄関や門の役割も担っていたそうです。
現在は伝承園の玄関口で土産処になっています。
事務局で受付を済ませていただき、それでは各自見学しますか。 |
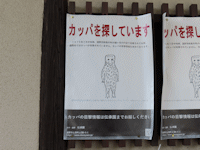 |
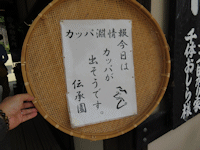 |
|
| カッパ探しているそうです |
今日は出そうなんだって |
|
| 以前来た時は、こちらの中には入らずでしたが、園内はふるさとの原風景を再現しているのですが、カッパ推しすぎてちょっと残念。 |
 |
 |
|
| では見学 |
早速いた |
|
|
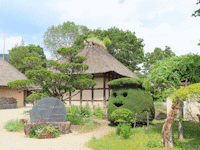 |
 |
|
いい感じの景色の中にも |
いた |
芝や草じゃなくて木が生えてきているぞ。
「板倉」は、壁が全て板で作られている納屋で、農作業を行う場として使用されました。 |
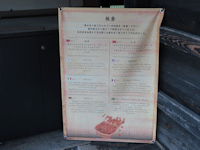 |
|
|
| 解説 |
|
|
遠野物語についてのい説明がありました。
そういえば、遠野物語は詳しくは知りませんね。 |
 |
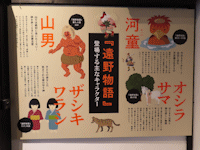 |
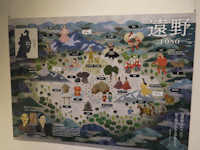 |
| 河童や座敷童の話 確かにその印象 |
いろいろでているんだ |
遠野のそれぞれの地域の話 |
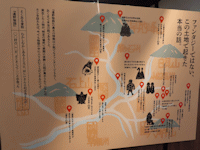 |
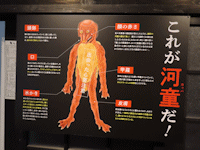 |
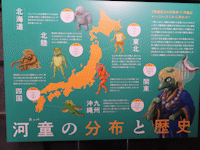 |
土地のノンフィクション
一般的な昔話は「昔々あるところに」
遠野物語は「〇〇村の□□が」 |
河童大解剖 |
日本中に生息しているらしい |
| 殿では、1975年(昭和50年)に河童がひっ歳に目撃されたそうですよ。 |
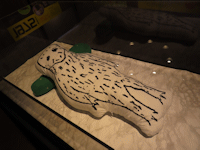 |
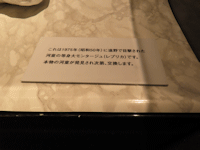 |
|
| 等身大モンタージュ |
だそうです |
|
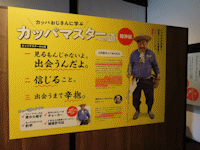 |
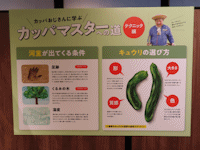 |
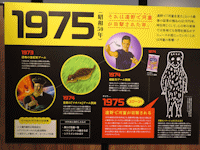 |
| 2代目カッパおじさんに学ぶ |
きゅうりも選ばないとだめなんだ |
ムーとかそんな世界 |
 |
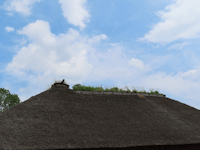 |
|
| 西側から |
芝棟 |
|
正面にまわります。
1750年(寛延3年)頃に建てられたといわれる最も古い時期の南部曲り家です。
直家から曲り家へ発展経過が垣間見られる貴重な建物ですよ。
遠野市小友町から移築しています。 |
 |
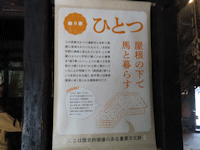 |
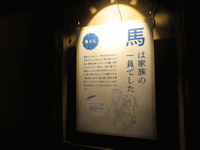 |
| おじゃましますー |
馬と人が暮らす曲り家 |
加須kの一因 |
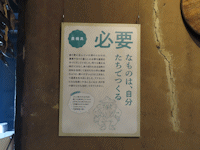 |
 |
 |
| DIYの精神が昔からありました |
使われていた頃の要す |
今も倉庫にしている? |
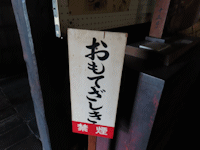 |
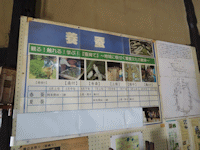 |
 |
| 時代を感じる案内 |
お蚕さんもしていたんですね |
座敷童!? |
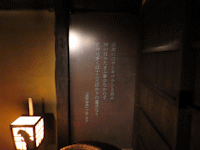 |
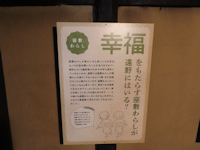 |
|
| ザシキワラシは遠野物語第17話に出てきます |
幸福をもたらしてくれますよ |
|
| ちょうど、語り部さんが昔話をお話してくださっていましたので、少しだけ聞いていきました。 |
 |
|
|
| 昔ながらの語り口調 |
|
|
| オシラサマという、遠野物語の第69話に出てくる、馬と娘の悲恋の物語があります。 |
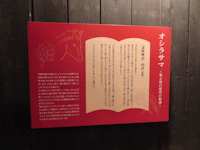 |
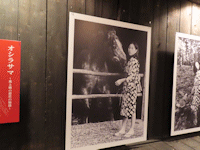 |
|
| 遠野物語第69話 |
馬に恋した農家の娘 |
|
|
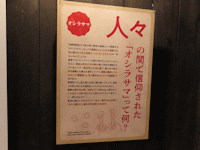 |
 |
|
オシラサマは家の神様 |
こういうフォルムだそうです |
オシラ堂に行ってみます。御蚕神堂とも書くようですね。
オシラサマを千体展示しています。オシラサマは、蚕の神さま、農業の神さま、馬の神さま、そして「お知らせ」の神さまとも言われています。 |
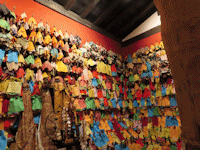 |
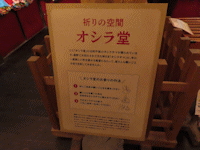 |
|
| オシラサマ |
解説 |
|
| オシラサマは今でも遠野の家63軒に169体おられるそうです。 |
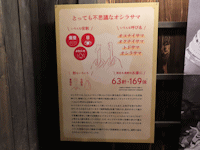 |
 |
|
| ほう |
いろいろなオシラサマ |
|
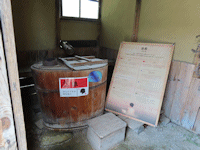 |
|
|
| 娘入浴中らしい |
|
|
 |
|
|
| 滑車を使ったのは1950年代らしい |
|
|
 |
 |
|
| 芝棟のある水車小屋 |
脱穀やわら打ちをしました |
|
 |
 |
|
| あれはなんだ? |
あーさっき行ったオシラ堂だね 御蚕神堂 |
|
「佐々木喜善記念館」ってのがありました。
遠野物語は、遠野地方の土淵村出身の民話蒐集家であり小説家でもあった若き日の佐々木喜善が、民俗学者の柳田國男に語った遠野の話が素になっています |
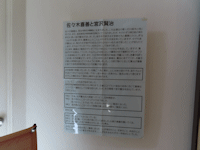 |
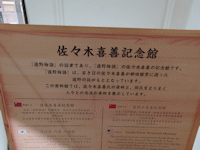 |
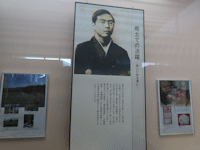 |
| 佐々木喜善は宮沢賢治とも交流がありました |
解説 |
日本のグリムと呼ばれたそうです |
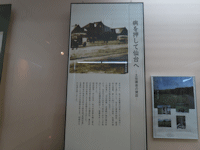 |
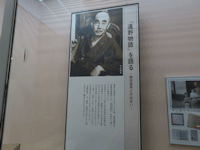 |
|
| 仙台で河北新報に連載小説を書いていたらしい |
柳田邦夫との出会い |
|
|
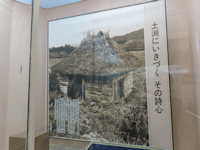 |
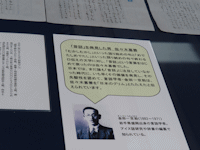 |
|
あれ?これは山口の水車小屋では |
「日本のグリム」の名は喜善病没の報を聞いた言語学者の金田一京助によるもの |
 |
|
|
| 佐々木喜善記念館でした |
|
|
 |
 |
|
| 乗込長屋に戻ってきました |
遠野ふるさと村のほうがよかったかな こちらは観光化されすぎ |
|
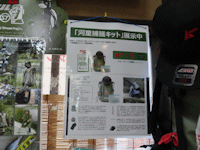 |
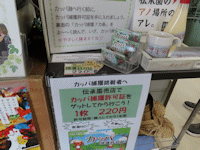 |
|
| 河童捕獲キットは展示だけなんだ |
捕獲許可証は期限切れですが持っています |
|
| お食事処で、カッパ焼き食べようかなと思いましたが、暑いしなぁ。 |
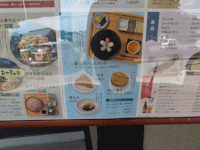 |
|
|
| やめておくか 前も食べたし |
|
|
 |
 |
 |
| キリンのホップ畑があります |
ホップ |
収穫は夏らしい |
 |
|
|
| 常堅寺さん |
|
|
歩いていくと、何やら騒がしい家族連れが。
河童発見ですか!? |
 |
|
|
| というより通らせてくれ |
|
|
 |
 |
|
| 清流ですよ |
カッパ淵 |
|
|
 |
 |
|
今回こそは釣り上げたいものです |
《クリックで動画再生》
釣れたのか!? |
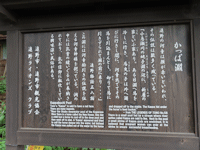 |
 |
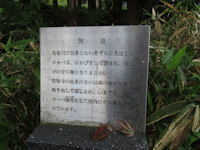 |
| 解説 |
ここを河童が泳ぐのだろうか |
常堅寺の火災では頭の皿の水で消火したらしい |
 |
 |
|
| 河童 |
狛犬
別にカッパこm犬もいます |
|
途中の、「かっぱの茶屋」でソフトクリームがありましたが、人多くて時かかかりそうなの絵断念。
伝承園の隣の酒屋さん「長龍商店」に、ホップ産地のうまいビールのポスターが。 |
 |
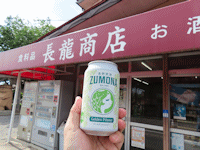 |
|
| 買っていくか |
ZUMONA |
|
| 伝承園を外から見ると、本当に古き良き日本の農村ですね。 |
 |
|
|
| 伝承園でした |
|
|
では出発です。
市道から県道160号を走り、R340へ。
そしてR283に入ります。
-14:50-
道の駅「遠野 風の丘」に寄ります。 |
 |
|
|
| ミニ四駆レースやっていました |
|
|
 |
|
|
| ZUMONAが種類豊富にある! |
|
|
ここでソフトクリーム食べようかなと思ったのですが、すんごい列。
集合時間に間に合わないな。
フードコートでは生ビール3種飲み比べというのもありましたが、小腹が減ったので、「漁師の魚屋」で海老カツ買いました。 |
 |
 |
|
| 漁師の魚屋 |
海老カツでかい |
|
 |
 |
|
| いいねー |
《クリックで動画再生》
パーンしました |
|
では出発です。
R283を猿ヶ石川沿いに走りR107に入ります。 |
 |
|
|
| 田瀬大橋を渡る |
|
|
県道27号kら市道に入ります。
-15:50-
旧伊藤家住宅にやってきました。
ここ、花巻市東和町田瀬の覚間沢地区は、江戸時代の旧盛岡藩の最南端に位置し、直屋(すごや)と南部曲り家の両方が建てられていた地域だったそうです。 |
 |
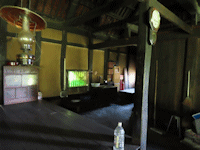 |
|
| 旧伊藤家住宅 |
結構こじんまり |
|
| 国の指定重要文化財の指定を受けた際には、南部曲り家の形状だったそうですが、1979年(昭和54年)の修理時に、母屋と馬屋が別々に建てられ、明治期以降に曲り家に改築されていたことがわかったため、当初の形式に復元したそうです。 |
18世紀(1700年代)前半にに建築されたと推定されています。
結構痛みは激しいです。 |
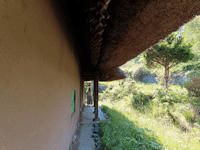 |
 |
 |
| 奥は足場がありまわれなかった |
芝棟がよくぞ残っていたという感じ |
雰囲気的にはいいですねー |
 |
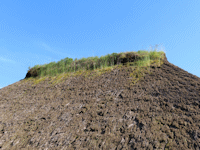 |
|
| こんもりしていてかわいい |
今回の芝棟はこれで見納め |
|
|
 |
 |
|
旧伊藤家住宅でした |
見学は16時半まで |
| ふと神栄菅興産のバスのライトを見たのですが・・・。 |
 |
|
|
| LEDポジション球が転がっている しかも2個も |
|
|
左右両方転がっていましたよ。取り出せないから放置なのかな。
予定は以上で終了。
では帰路につきますよ。 |
 |
|
|
| いい天気でよかった |
|
|
 |
|
|
| 釜石道をくぐる |
|
|
R107を走ります。
この道をずっと走れば横手まで行けるなぁ。100kmないですね。
-16:30-
釜石道・江刺田瀬ICから高速です。 |
 |
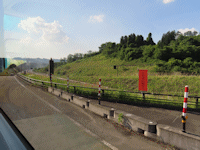 |
|
| インター入口 |
無料高速ですよ |
|
-16:40-
釜石道・花巻空港本線料金所を通過します。 |
 |
|
|
| ここから有料 |
|
|
 |
|
|
| 高速降ります |
|
|
市道を走っていきます。
-16:55-
JR東北本線・花巻駅に寄ります。
関東から参加の方は、ここから列車で帰路に。おつかれさまでしたー。 |
 |
|
|
| 花巻駅でした |
|
|
市道から県道297号、県道298号、県道286号と走ります。
-17:10-
いわて花巻空港に到着しました。 |
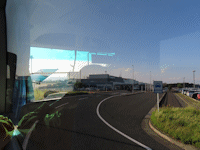 |
|
|
| 初めての花巻空港 |
|
|
新栄観光さん、2日間ありがとうございましたー。
一応、バスを降りたら解散。連泊する人もいるし、ここでそれぞれ帰路につきますよ。 |
 |
|
|
| では空港ビルへ |
|
|
最後の買い物します。
バックパックには入りきらないので、エコバックに入れて機内持ち込みしよう。
-17:35-
まだ時間があるので、「いわて花巻大食堂」でお茶するかな。
夕食は、お土産に前沢牛のハンバーグを買ったのでそれ食べよう。 |
 |
|
|
| いわて花巻大食堂です |
|
|
結構混んでいますねー。先に入っていた、前田由利さんたちと同席させてもらいます。
チロルのチーズケーキが美味しそう。 |
 |
|
|
| ということでコーヒーセット |
|
|
同席の方は、皆さん、ぴょんぴょん舎の冷麺食べられていましたが(笑)
-18:10-
30分前ですね。
さて、そろそろ保安通過しておきますか。
帰りも水筒の中身を確認され通過。
2番ゲートに向かいます。
-18:40-
離陸予定時間に登場開始です。 |
 |
 |
 |
| ボーディングブリッジで移動 |
同じ時間に離陸のフジドリームエアラインズ(FDAはボーディングブリッジもう外れている) |
乗るJAL2190便 |
帰りの機材は、エンブラエル170です。
窓側に座り、通路側は若い男性で、何やら司法試験の勉強してましたよ。 |
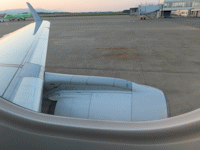 |
 |
 |
| エンジン横 |
FDAはもうタキシングに入ります |
夕暮れですね
2日間楽しかった |
-18:50-
10分遅れで扉が閉まり、ボーディングブリッジが離れます。 |
 |
 |
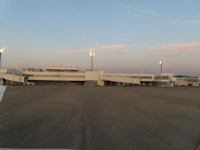 |
| さぁ離陸です |
トーイングカーがバックさせていきます |
いわて花巻空港でした |
| グランドハンドリングクルーの皆さんが手を振ってお見送りしてくれます。 |
 |
 |
|
| トーイングカー待機 |
こちらも手を振り返す |
|
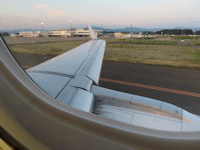 |
 |
|
| さらば東北 |
《クリックで動画再生》
"Roundabout"YES
関西に向け帰ります |
|
|
 |
 |
|
離陸して空港の上を旋回して南へ |
田んぼに映る月 |
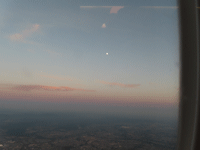 |
 |
 |
| いいねー |
夕暮れのフライトもいいね |
宮城県あたりかなぁ |
 |
|
|
| ルート上なら多分そうだな |
|
|
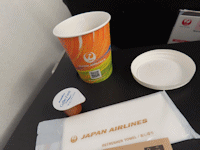 |
|
|
| コーヒーいただく |
|
|
| 日没で景色が見えないので、機内誌のSKY WORDを読んでおこう。 |
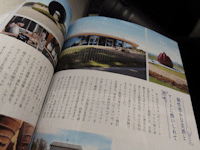 |
 |
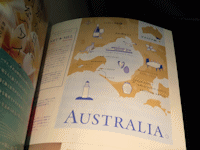 |
| オーストラリアに草間彌生作品があるんだ |
ワイナリー巡りかぁ |
メルボルン周辺 |
| そういえば昨日、前田由利さんが弘前レンガ倉庫美術館の近所の美味しそうなアップルパイの店の記事を読んだと言われていたので、改めて読んでみました。 |
 |
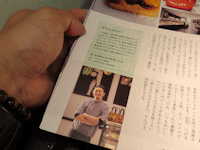 |
|
| おー |
いいね |
|
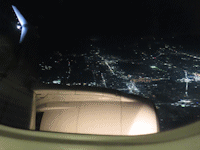 |
|
|
| 大阪上空 |
|
|
-20:25-
大阪国際空港(伊丹空港)に着陸します。 |
 |
|
|
《クリックで動画再生》
"Owner Of A Lonely Heart"YES
ただいまー |
|
|
タキシングして駐機します。
ここからタラップで降りて、バスで移動するらしいです。 |
 |
 |
|
| タラップがやってきた |
ドッキング |
|
| しかし、バスが来るのが遅れているとのことで、なかなか出られません。 |
 |
|
|
| 飛行機の洗機場 |
|
|
 |
|
|
| やれやれ |
|
|
しかし、隣の人がなかなか立ち上がってくれないので出られません。
6列目にいるのに・・・。
後ろのほうに座った彼女?を待っていたのか、出たのは最後のほうでした。 |
 |
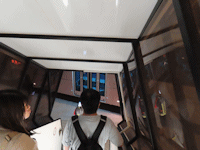 |
|
| タラップを下る |
満員で次のバス待ち |
|
 |
|
|
| やれやれだよ本当に |
|
|
 |
|
|
| がんばって帰ろう |
|
|
すぐに大阪モノレール・大阪空港駅から乗ります。
-20:55-
大阪モノレール・蛍池駅で降り、阪急に乗り換えます。 |
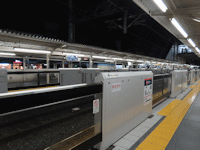 |
 |
|
| ホームドアができていた |
10分ほど待って宝塚行に乗る |
|
| 阪急・池田駅にSDGsトレインのラッピング電車がいました。 |
 |
|
|
| 大阪梅田行きのSDGsトレイン |
|
|
-21:25-
阪急・宝塚駅で西宮北口方面に乗り換えます。 |
 |
|
|
| 宝塚ー |
|
|
-21:40-
阪急・小林駅で降りて、てくてく歩いて帰りましたよ。
ただいまー。予定より半時間ぐらい遅くなりましたよ。
早速ハンバーグ焼くか。 |
 |
 |
|
| 美味献上前沢牛生ハンバーグ150g |
急いで作ったらちょい焼きすぎた |
|
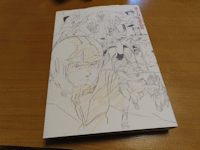 |
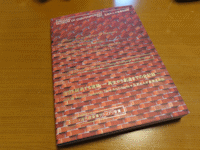 |
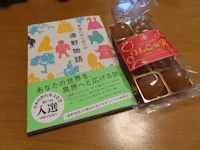 |
| 青森県立美術館で買った安彦良和の図録 |
弘前れんが倉庫美術館の図録 |
リンゴの実は弘前
遠野物語はふるさと村 |
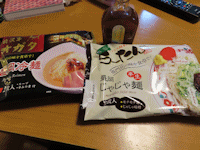 |
 |
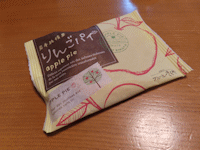 |
クラフトコーラは弘前
麺は岩手山SA |
ふるさと村で買った南部せんべい |
岩手建築士会の方々にいただいたアップルパイ |
 |
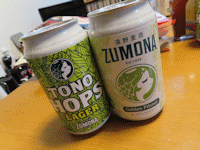 |
|
| 花巻空港で購入 |
遠野麦酒ZUMONA |
|
本日の東北移動距離 155km
通算の東北移動距離 388km
結構な詰め込みでしたが、楽しく芝棟を堪能した2日間でした。
企画いただいてありがとうございますー。
また機会があれば参加したいですね。
そして、芝棟がこれからも少しでも残っていってくれるといいなぁ。 |
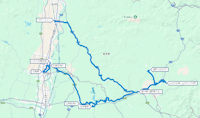 |
| 6/8移動マップ |
←1日目に戻る


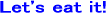
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.