 Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。
Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。※ここに掲載のカスタムを参考にされる場合はあくまでも個人の責任でお願いします。
 Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。
Rockzの愛車だったTMAX530と、バイクの話題の部屋です。
※ここに掲載のカスタムを参考にされる場合はあくまでも個人の責任でお願いします。
Last Update 2026/01/03
| 2001年にこれまでなかった「大型二輪免許で乗るスクーター」という、メガスクーターなるカテゴリで、YAMAHA TMAXが登場しました。 「オートマチックスポーツ」というカテゴリは二輪の世界に新しい風を吹き込んだと実感しています。 Honda Dio(50cc)、Honda SPADA(250cc)、Honda VFR400(NC30)(400cc)と乗り、その後一旦二輪から遠のいてHonda LEAD90に乗っていましたが、再びバイク熱に火かついて、大型バイクに乗ることになりました。 そして、2002年3月8日から15年間、2017年3月11日まで、4台のTMAXを乗り継いできました。 理由あって、現在二輪からは完全に降りていますが、また乗れる日が来ればいいなぁと思います。 とりあえず、過去に乗ったTMAXたちです。 |
YAMAHA TMAX530 (EBL-SJ12J) 2013.03.30〜2017.03.11 走行距離 37,949km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with JADE |
YAMAHA TMAX (EBL-SJ08J) 2008.12.28〜2013.03.09 走行距離 45,109km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with STREAM |
YAMAHA TMAX (BC-SJ04J) 2005.05.02〜2008.12.27 走行距離 76,142km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with Edix |
YAMAHA TMAX (BC-SJ02J) 2002.03.08〜2005.04.16 走行距離 44,186km 詳しくはこちら |
 Left View |
 with ODYSSEY |
| フランス人の冒険家、ティエリー・サビーヌの発案により1978年の年末に始まり、例年1月に開催されているラリーレイド競技大会のダカール・ラリー。 私が冒険の扉を示す。開くのは君だ。望むなら連れて行こう。 とティエリー・サビーヌは語りました。 当初はフランス・パリをスタートし、アフリカ大陸に渡り、セネガルの首都・ダカールでゴールというものでしたが、現在はサウジアラビア1国のみを走るラリーとなっており、「ダカール」は名を残すのみとなっています。 本日、1月3日から17日まで、紅海沿岸の港町ヤンブーをスタートし、全長約8,000kmのルートを走破する中、5,000kmがタイム計測区間となります。 また、ラリーの中間地点である首都リヤドでは、参加者がしっかりと休息を取るための休息日が設定されています。 そして、フィニッシュもヤンブーとなり、砂漠の中心部と首都リヤドにも6つのビバークが設置されます。 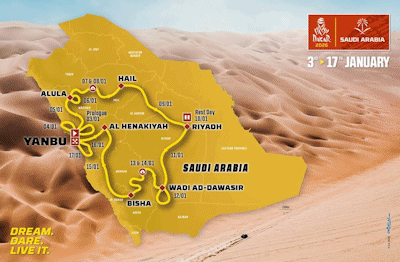 今大会のルート 今大会のルート2輪(Bike)は全車両最大排気量450cc、シリンダー数は単気筒のみに制限されます。 ライダースーツにはエアバッグの装着が義務付けられます。ライダーはグループ1(エリートクラス)とグループ2(ノンエリートクラス)に分かれ、総合トップ10フィニッシュまたはステージウィン経験者は黄色いゼッケンのエリートクラスに強制的にカテゴライズされます。 車両は、以前はプロトタイプまたは大規模に改造された市販車を用いるクラス1(スーパープロダクション)と、小規模改造の市販車であるクラス2(マラソン)に分けられていて、エリートクラスはクラス1車両のみが使用可能でした。 2022年から世界ラリーレイド選手権発足に伴い、同選手権の規定であるRallyGPが導入され、旧クラス2はRally2へと改称されています。最大時速制限はRallyGP、Rally2共に160km/hとなっています。 今回もKTMとHondaの争いでしょうかね。 まずは、KTM(Red Bull KTM Factory Racing)は昨年勝者の#1 ダニエル・サンダース、昨年4位の#77 ルチアーノ・ベナビデス、#73 エドガー・カネの3選手を擁して、450 Rally Factoryで参戦します。  KTM KTM対するHonda(Monster Energy Honda HR)は、2度ダカール制覇の#9 リッキー・ブラベック、#10 スカイラー・ハウズ、#42 エイドリアン・ヴァン・ベヴェレン、#68 トシャ・シャレイナの4選手を擁して、CRF450 RALLYで参戦します。  Honda Hondaなお、Hondaは、Rally2チームも出場します。 Monster Energy Honda HRC Rally2です。 また、トライアルライダーの藤原慎也選手が今大会唯一の日本人ライダーとして、RSMOTO HRC Race Serviceでダカールラリーに初挑戦します。 Hondaは2024年にチャンピオンになりましたが、昨年は逃しています。 今日から17日まで、がんばってほしいなぁ。 |
| YAMAHAが11月20日に「TMAX560 25th Anniversary」として発表をしていました。 25周年ですかー。 このHPを開始する際に、TMAXに乗ろうということで、Motorcycle Roomのコンテンツを加え、初代TMAXを購入。 その後、15年間で4台(4世代)のTMAXを乗り継いで、いろいろあってバイクから降りましたが、25周年モデルですか。  これね これねぱっと見は、これでいいのか?25周年カラーと思ったのですが・・・。 「TMAX560 25th Anniversary」は、最新の「TMAX560」に、2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと装備を加えた特別な一台として仕上がりました。 ということらしいので、まぁ、過去へのオマージュってとこなのでしょうか。 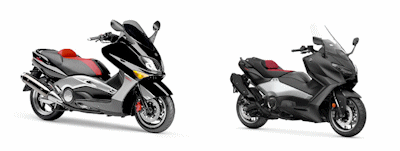 左が2005・TMAX SPECIAL 左が2005・TMAX SPECIAL主な特徴は、1)メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装、2)専用表皮を用いたレッド/ブラックの専用シート(赤色ダブルステッチ縫製、専用シートタグ)、3)サイドカバーに配置したTMAXレッドクロームエンブレム、4)レッグシールド中央部の25周年記念特別エンブレム、5)起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ、6)アルミ本来の素材感が映える切削ホイールなどです。 とのこと。 上級モデルの「TMAX560 TECH MAX ABS」には、「MT-09」などのエンジンに採用し好評の、金属よりも金属らしい質感を持つ"クリスタルグラファイト"を新たなブランドカラーとして車体色に採用。"プレミアム&高品質"をもたせるとのこと。 TMAX560 TECH MAX ABSは来年1月20日発売で1,644,500円、MAX560 25th Anniversary来年2月25日発売で1,507,000円だそうですよ。 100万円切っていた初代の頃が懐かしいなぁ・・・。 |
| 2年ぶりに、「Japan Mobility Show 2025」が31日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されます。 2023年からこの名称ですが、それまでは「東京モーターショー」と言っていました。 最後に行ったのは2017年のこと。 大阪モーターショーも最後に行ったのは2019年のこと。こちらは「Japan Mobility Show Kansai 2025」と名を変え今年は12月5日荒7日に開催されます。 最後に行った頃には、観ていてもワクワク感がなくなってきたなという感想でした。 EVとか省エネとか、環境配慮とか。 すべて正論なんでしょうね。でも、今でも自分の中ではエンジンの音とオイルの匂いが車であり、バイクなのですよね。 そこを覆すほどの面白さ、例えば走りなどあればまだワクワク感はあるのでしょうけど。 特に車は、EV、ハイブリットが進んで、あまりワクワクしません。 バイクも、バイク人口が減ってラインナップも少なくなってきたこともありますが、それだからこそ、YAMAHA NIKENやTRICITYは、どんな走りなのか乗ってみたくなるし、あと、小型のギア付きバイクなんかも面白そうと思ったりします。 そんなわけで、わざわざモビリティショー観に行こうという気が起きないんですよね。 今年の各メーカーは、どんなの出すのかなと何気に見ていたら、YAMAHAが面白いのを出しています。 TRICERA proto  前2+後1輪 前2+後1輪おー、なんか面白そうだぞ。 でもこれはバイクではないね。 3輪パッケージのフルオープンEVです。感性に訴える刺激的な旋回性能と、新感覚の操縦感を併せ持ち、意のままに操るための習熟プロセスさえ楽しい3輪手動操舵(3WS)の実走コンセプトモデルです。 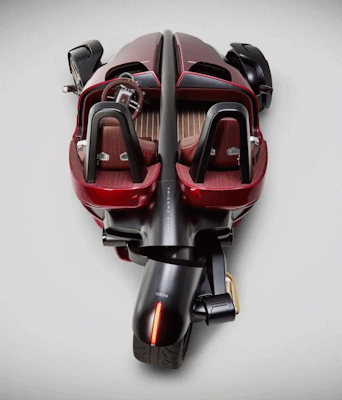 前後舵角がとれる 前後舵角がとれる前後輪操舵可能な車両の特徴である旋回応答性の高さと旋回時のドライバー感覚とのつながりに着目し、人間研究視点で最も FUN を感じる旋回制御とすることで、異次元の人機一体感を実現。 また、走行音をチューニング&調律するサウンドデバイス「αlive AD」を搭載し、操縦に没入するドライバーの高揚感を増幅します。 3輪構造を際立たせたセンターフレームによるアーチ型シルエットに加え、人間空間と機能空間の対置表現により独創的なデザインを実現したとのこと。  ちょっとノスタルジック ちょっとノスタルジックでもカッコイイですね。 日常乗りには厳しいですが、多分、乗ると楽しいんだろうなぁ。 |
■ RockzGoodsRoom ■ Sitemap Copyright(C) RockzGoodsRoom All Rights Reserved.